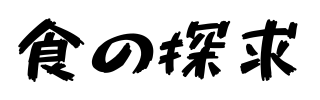佐賀県の特産物といえばブランド和牛の中でも常に上位にランクインしている佐賀牛が有名ですが、有明海や玄界灘に面していることもあり、アジや鯛、さらにはムツゴロウ、メカジャ、ワラスボ、えつなど定番から他県ではあまり聞き馴染みのない種類の魚介もたくさん漁獲されています。他にも葉物野菜のアイスプラントや嬉野茶、ブランド米のさがびよりなど幅広く生産し親しまれていますが、県外ではあまり知られていない特産物やグルメも多いです。今回はそんな佐賀県で人気がある意外な特産物やグルメについて紹介していきたいと思います。
イカ
フライや刺身、煮物などさまざまな料理に使える“イカ”は、北海道や青森県をはじめとする東北、富山・石川・兵庫といった日本海側などで漁獲されることが多いため、佐賀県の特産物と言われてもピンとこない人も多いのではないでしょうか。実際に佐賀県においてイカの漁獲量は全国の中でも20~25位あたりに位置付けることが多く、漁獲量だけで見ると同じ九州である長崎県の方が10倍近い量を漁獲していることもあって、主な産地として名前が上位にあがることは少ないです。しかし、そんなイカの主要産地を抑えて「日本一イカが美味しい県」として認知されているのが佐賀県になります。県内でも特に唐津市呼子町(よぶこ)は美味しいイカの産地として有名で、玄界灘で獲れる「呼子のイカ」は鮮度の高さと甘さ、そして特徴的な食感が評価の高さに繋がっており、なかでも上品な甘さとコリコリとした食感を感じられる剣先イカ(ヤリイカ)の人気が高いです。また、名物の活創りはイカを新鮮なうちに腕の良い職人が手早く捌くため、普段見慣れている刺身とはまったく違う透き通った透明の状態で提供されるのも大きな特徴となっています。味わいや食感の良さはもちろんですが、その見た目の美しさがより美味しさを引き立たせてくれることから、味覚・視覚合わせて呼子のイカは日本一と呼ばれているのです。
県内の中でも最北端に位置する呼子町は、2005年に唐津市をはじめとする8つの市町村によって合併しており、現在は唐津市呼子町となっています。人口も5,000人ほどと小さな町ではあるものの、美味しいイカを求めて訪れる観光客は年間100万人とも言われ、朝市や活造りを提供する飲食店を目的に訪れる人も多いです。呼子のイカが美味しいといわれる理由の1つには、九州の北西部に広がり漁場でもある玄界灘が大きく影響しています。玄界灘は対馬海流や黒潮が流れ込む環境であるため、豊富な栄養塩によって大量のプランクトンが発生します。さらに、この海域の大陸棚は浅く、光が届きやすいことからプランクトンが繁殖しやすいため、エサを求めて多様の魚が集まりやすくなっており、こうした恵まれながらも厳しい環境で育ったイカだからこそ、特有の食感や甘みが生まれているのです。また、イカは人の手が触れるだけで火傷してしまうほどデリケートな生物であるため、温度や取り扱いにも注意が必要になります。そのため、呼子で漁獲されるイカは釣り上げた直後に素早く生け簀に移してイカが受けるダメージを減らし、出来るだけ人の手が触れる時間を短くしています。この作業が鮮度の高さに繋がっていますが、これに加えて呼子では漁港で行われる一般的なセリにはかけずに契約している飲食店に直接配送し、各店舗が持つ生け簀へ移すという独自の流通ルートを取り入れていることが多いです。漁師だけでなく飲食店側もイカの扱いや管理に力を入れていることが、食べる瞬間までイカを新鮮に保つことに繋がり、美味しさと美しさを提供することが出来るのでしょう。
呼子では剣先イカが有名ですが、他にも濃厚な甘みとモチモチしたと食感が楽しめるアオリイカ(ミズイカ)やバランスが良く厚みがありながらも柔らかいコウイカなど、その時期によって特徴の違う種類のイカも食べることが出来るため、訪れたタイミングによって異なる味わいや食感の違いを楽しむのもおすすめです。また、塩辛や醤油漬け、さきいか、名産品にもなっているいかしゅうまいなど、県内ではイカを使った多種多様の加工品も多く販売されており、特にイカを日光に当てずに乾燥させた一夜干しは旨みがギュッと凝縮しながらも適度な水分が保たれているため柔らかく、干物の中でも特に美味しいと評判が高いことからお土産や贈り物としての需要も高いです。初めて呼子のイカを食べた人はその美味しさから衝撃や感動を覚える人も多く、忘れられないほどともいわれているため、ぜひ佐賀県に訪れる際には最北の呼子まで足を延ばして、新鮮で美しく美味しい呼子のイカを思う存分堪能してもらいたいです。
佐賀海苔
“佐賀海苔”は佐賀県の有明海で生産されている海苔のことであり、他県産の海苔と比べると黒紫色をした艶のある色味やくちどけ・のどごしの良さ、香ばしい香りと甘みを含んだ旨みを感じられるのが大きな特徴です。海苔といえば風味、食感のよさから全国でも「有明海苔」が有名ですが、生産している県などは関係なく、有明海で収穫された海苔を総称して「有明海苔」と呼んでいます。その中でも特に品質が高く味も良いと評価されているのが佐賀海苔であり、有明海全体を見ても佐賀県が一番の生産量を誇っています。その生産量は2021年まで19年に渡って全国においてもトップシェアを維持し続けてきました。さらに佐賀海苔の内、一番摘みの初物でたんぱく質の含有量や香り、柔らかさ、艶、色、形など7つの厳しい評価基準を満たした海苔だけが「佐賀海苔 有明海一番」というブランド海苔に認定され、最高級海苔として販売することが出来ます。その数はなんと1万枚に3枚しか出ないと言われるほど貴重であるため、環境などによる不作時には基準を満たすことが出来ず販売出来ない年もあるほどです。
日本の海苔の歴史は非常に古く、縄文時代にはすでに海苔を食べていた可能性があると言われており、江戸時代には東京湾で始めた養殖をきっかけに身近な食べ物へと変化していきました。現在は日本一として名もあがるほど海苔の養殖が有名な佐賀県ですが、本格的に養殖を始めたのは昭和28年の戦後のことであり、思いのほか歴史は浅い方となります。しかし、有明海が海苔を養殖するのに非常に適した環境だったことや佐賀県の地形、独自の栽培方法などにより瞬く間に主要生産地へと成長していきます。有明海は世界でも有数の干満差があり、その差は最大で6mにもなります。この干満差によって満潮時には海水に浸かっている海苔網が海面上に現れて光合成が促進されるため、海水に含まれる栄養と太陽の力を交互に吸収することよってアミノ酸が増殖し、旨みや甘み、香りを強く感じるようになるのです。また、有明海には九州最大の筑後川をはじめとする多くの河川が流れ込み、ミネラルなど山林で作られる栄養分をたくさん含んだ真水が混ざっています。この淡水と海水が混ざり合うことが海苔の養殖に最適な塩分濃度を作り出し、柔らかさや美味しさに繋がっていきます。さらに佐賀県では、昭和後期に起きた干潟の異常干ばつにより養殖海苔が大きな被害を受けたことからリスクを減らすため、生産者と県が連携を取って気象状況や海の様子、塩分、水温などの情報を共有する「集団管理方式」を取り入れており、この情報の共有こそが佐賀県の養殖業を発展させた要因となったそうです。他にも県が品質を向上させる取り組みを始めたことなど、多くの人の協力や努力の結果、高品質の佐賀海苔を生産することに成功し、日本一の養殖海苔を確立することが出来ました。
近年は小雨続きや赤潮の被害によって海苔の成長に欠かせない海の栄養塩が不足し、海苔の色落ちや他生物による食害などが重なり生産量は減少しています。しかし、そんな環境下でも質の高い海苔を生産出来るよう、日々さまざまな研究や努力が県内では行われており、将来的には海の影響を受けない陸上での養殖も視野に入れているそうです。日本人にとって親しみ深いおにぎりには欠かせない海苔ですが、アレンジ力は抜群で、サラダや揚げ物、卵焼き、さらにはパスタやスープなどに加えるだけで海苔の香ばしい風味と奥深さ、そしてアクセントを与えてくれます。また、定番の焼き海苔や味つけ海苔、生、乾燥、板状なのかバラなのかなど加工方法や形状によっても使い方も風味も変わってくるため、使いやすいタイプを見つけて普段の食生活に美味しい佐賀海苔を取り入れてみてはいかがでしょうか。
ごどうふ/温泉湯豆腐
大豆から作られる豆腐は、味噌汁や冷ややっこなど日本食では馴染み深い食べ物ですが、佐賀県では一般的な豆腐とは少し異なる特徴を持つ豆腐が2種類あります。1つ目は“ごどうふ(呉豆腐)”という豆腐の種類です。通常、豆腐を作る際には豆乳ににがりを加えて作りますが、それに対してごどうふは葛粉やでんぷんを使って作られるため、柔らかくプルっともちもちとした食感に仕上がるのが特徴です。葛粉を使うという部分はごま豆腐と似ているものの、ごまが入っていない分より粘性が高く、味わいは普通の豆腐とほとんど変わりません。酢味噌やわさび醤油、すりごまと砂糖を加えたごま醤油などをかけて副菜として食べるのが定番の食べ方となりますが、プリンのような艶と食感も持ち合わせているため黒蜜やきな粉をかけてデザートの代わりとしても食べられています。また、形が崩れにくい特徴から天ぷらにすることも可能で、衣のサクッとした食感とごどうふのとろけるような食感は揚げ出し豆腐とはまた違った美味しさを味わえます。
昭和初期に佐賀県の有田町で誕生したごどうふは、水に浸してすり潰した大豆を圧力鍋などで煮ることで出来る「呉(ご)」から豆乳を搾り作られたため、呉豆腐という名前がついたとされています。また、発祥としては有田町の豆腐屋が大豆の買い付けのために長崎に訪れた際、中国人から葛を使った豆腐の作り方を教えてもらったことから始まりました。もともとは精進料理の一つとして食べられていたごどうふでしたが、次第に家庭でも食べられるようになり、郷土料理として浸透していったのです。そのため、冠婚葬祭などでもよく提供されますが、現在も有田町を中心に普段の食事として親しまれている食べ物になります。
もう1つの異なる特徴を持つ豆腐は、日本三大美肌の湯にも選ばれている嬉野温泉の名物“温泉湯豆腐”です。嬉野温泉は佐賀県の西部、嬉野市にある温泉であり、この温泉街で親しまれている温泉湯豆腐は江戸時代から食べられていたと言われるほど歴史のある食べ物です。湯豆腐は柔らかい絹ごし豆腐を使えばつるっとしたのどごしの良い食感、木綿豆腐を使えば大豆の味わいをしっかりと楽しめる料理ですが、嬉野温泉で食べられている湯豆腐は一般的な湯豆腐とはまったくと言っていいほどの別物であり、ふわふわでクリーミー、口に入れると溶けてしまうような不思議な食感が大きな特徴で、大豆の旨みと甘みも一緒に味わうことが出来ます。しかし、温泉湯豆腐で使われている豆腐も基本的には絹ごし豆腐や木綿豆腐など一般的な豆腐と変わりありませんが、なぜそこまで食感に大きな違いが生まれるのでしょう。それは嬉野温泉のお湯が大きく関係しています。
1300年の歴史を持つ嬉野温泉の泉質は、無色透明の弱アルカリ性でナトリウムが多く含まれているため、皮膚を乳化して肌を滑らかにし、美肌にする効果があるとされています。その温泉水を使って豆腐を煮ると豆腐の持つたんぱく質が分解されて角が丸くなり、とろけるような食感へと変化するのです。そのため、はじめは透明だったお湯は次第に豆腐が溶け出して豆乳のような白濁した湯汁に変わり、色が変わることで食べごろを見極めることが出来ます。また、温泉水にはミネラルが豊富に含まれており、このミネラルが豆腐の風味をまろやかにしてくれるため大豆の旨みや甘みを感じやすくなっているのです。この温泉水を使った湯豆腐は江戸時代から地元の人や嬉野温泉に訪れる旅人たちに親しまれており、現在も旅館の朝食や飲食店の定番メニューとして人気があります。さらに豆腐を茹でた後の湯汁にも大豆の旨みが染み出しているため、野菜やきのこ、魚、肉などを入れて鍋としても食べることが出来、締めの雑炊など最後の最後までしっかりと堪能することが出来ます。しかも通常の豆乳鍋と違い、豆腐から出た旨みを活かしたスープであるためくどくなく、嬉野の温泉水でしか作り出せない風味や美味しさを楽しむことが出来ると言われています。
実は佐賀県は国内でも有数の大豆の生産地であるため良質な大豆が昔から身近にあり、そんな環境だったからこそごどうふや温泉湯豆腐が誕生し親しまれてきたのでしょう。この二つの豆腐以外にも、豊かな風味となめらかな食感を味わえる「おぼろ豆腐」や湯豆腐のために嬉野産大豆のフクユタカを使用して作られた木綿豆腐「嬉野温泉湯どうふ」なども販売されているため、豆腐が好きという方はぜひ、佐賀県の個性豊かな豆腐を味わってみて下さい。
シシリアンライス
“シシリアンライス”という料理を聞いたことはありますか?シシリアンライスとは、温かいごはんの上に生野菜と甘辛く炒めた牛肉を乗せてマヨネーズをかけた料理であり、佐賀県のご当地グルメやソウルフードとして親しまれています。お店によってはごはんが見えないほどの野菜が盛りつけられているため、サラダ感覚で食べられるように思えますが、ごはんと肉も一緒になっていることでしっかりとした食べ応えがあり、それぞれの食材の異なる食感や温度も一緒に楽しめるのが特徴です。お店によって少しずつバリエーションが違うのも魅力で、甘辛く炒めた牛肉の代わりに豚肉や鶏肉を使う場合やたまねぎなどの野菜も一緒に炒めているもの、焼き肉のたれ・てり焼き・カレー風味など味つけの仕方が違うもの、ステーキやローストビーフを使っているもの、温玉や素揚げした野菜をトッピング、マヨネーズの代わりに自家製のドレッシングを使うなどなど、基本的な形は維持しながらも、各店舗の個性や工夫を最大限に味わえるのもシシリアンライスの良さと言えるでしょう。
昭和50年頃に佐賀市にある喫茶店でシシリアンライスは誕生したと言われています。当初は玉ねぎやピーマンなどのあり合わせの食材を使った賄い飯だったそうですが、食べた従業員からの評判が良かったため見た目などを改良して新しいメニューとして加えたのがはじまりとなっています。多くのシシリアンライスには生野菜にトマト・レタス・キュウリ、そしてゆで卵が使われていますが、これはトマトの赤、キュウリなどの緑、ゆで卵の白がイタリア国旗の三色旗をイメージさせることや考案者がイタリアのシチリア島を舞台にした映画「ゴッドファーザー」に憧れを持っていたことからシシリアンライスと名付けられたとされているため、由来となり誕生当初から使われている食材を変わらずに使っているお店が多いのです。賄い飯から生まれたシシリアンライスですが、おもしろい食感と想像以上にマッチする味わいが話題となり、佐賀市内の喫茶店を中心に提供する飲食店が増え、定番メニューとして浸透していきました。2000年以降には全国でB級グルメのブームがおき、B-1グランプリが開催されるようになると、各地でご当地グルメによる地域おこしが行われるようになりました。それに伴い、シシリアンライスもメディアで取り上げられたことをきっかけに佐賀県でPRする取り組みが行われ、さらには九州B-1グランプリの第一回大会でシルバーグランプリを受賞したことによって市外や県外にも認知されるようになったのです。そのため、提供する飲食店も年々増え、現在ではカフェやレストラン、さらには居酒屋や焼き鳥屋など約40軒以上の飲食店でオリジナルのシシリアンライスを食べることが出来ます。
ちなみに、ごはんに生野菜と肉というシシリアンライスと似た組み合わせの料理には沖縄のご当地グルメである「タコライス」がありますが、タコライスは甘辛く炒めた牛肉の代わりにタコミートというスパイシーに味付けをしたひき肉と玉ねぎが乗っており、他にもチーズやアボカド、トマトのサルサ(ソース)などタコスの具材を使って作られていることから全体的にピリ辛な味わいとなっています。どちらかと言えばシシリアンライスの方が日本人にとって馴染みのある味つけをしているため、タコライスと合わせて食べ比べをしてみるとよりシシリアンライスの美味しさやそれぞれの魅力を感じることが出来るでしょう。なかなか県外では食べることが出来ないちょっとマイナーなご当地グルメでもあるため、佐賀県を訪れる際には一度は必ず食べてもらいたい料理でもあります。
丸ぼうろ
佐賀県を代表する郷土菓子であり銘菓の一つでもあるのが“丸ぼうろ”です。丸く少し平べったい形をした丸ぼうろは、小麦粉・卵・砂糖を主原料にして作られていますが、添加物も少なく砂糖も控えめであるため優しく上品な甘さを感じられ、表面のサクサクとした食感と中のふんわりとした2つの食感を楽しめるのが特徴です。また、少し時間が経つとしっとりとした食感にも変化し、素朴ながらもシンプルであるが故に子供から大人まで年齢問わず、幅広い年代の人に愛されているお菓子となっています。なかには、口当たりをよくする目的や奥深さを出すために蜂蜜を使う場合や膨らみを出すために重曹・ソーダを混ぜているもの、香ばしさや風味をよくするためにごま油や黒糖を加えているものなど、主原料に材料をプラスして作られている商品も多く、製造メーカーによって少しずつ特徴の異なる丸ぼうろを味わうことが出来ます。
丸ぼうろは16世紀~17世紀にかけて、日本では江戸時代にあたる時代に長崎を経由して伝来した南蛮菓子の一種とされています。オランダ語で丸い形を意味するボーロが語源という説や日本を含めた東洋を紹介したマルコ・ポーロにちなんで丸ボーロと名付けられたと言う説など諸説あると言われていますが、ポルトガル北部の都市に伝わる「カヴァカ・フィーナ・デ・カルダス」という郷土菓子が起源となっている説が有力とされています。起源となるカヴァカは丸ぼうろと違い、本来はクッキーのような硬い食感の焼き菓子になりますが、小麦粉の質の違いなどにより主原料や製法はほとんど同じであるにも関わらず、まったく違った焼き菓子に仕上がったそうです。これを実際に食べたポルトガル人が「カヴァカよりも柔らかくまるでケーキのよう」ということからポルトガル語でケーキを意味する「ボーロ」という言葉を使って表現したため、丸ぼうろと名付けられたと言われています。この他にも、佐賀市内で古くから営業している老舗菓子店が考案したという説もあり、名前や発祥においていくつもの説が残り、明確になっていないのも古い歴史であるからこその理由なのかもしれません。いずれにしても、佐賀市からはじまり現在は県を代表する銘菓として定番のお土産などとして親しまれているのには変わりないでしょう。
丸ぼうろはシンプルな材料で作られているため、自宅でも簡単に作ることが出来るのも良さであり、ホットケーキミックスを代用すればさらに手軽に作ることが出来ます。もちろんそのまま食べても美味しいですが、好きなジャムやバターを丸ぼうろでサンドしたり、トーストをしてカリっとさせる、牛乳につける、アイスを添えるなどさまざまなアレンジが出来るのも余分なものを使っていないが故の魅力になります。また、優しい甘さであるため、おやつ以外にもハムやレタス、ハンバーグなどの好きな具材を挟んでサンドイッチやハンバーガーとして食べることも可能です。メーカーによってはすりごまやケシの実、ジャムを練り込んでより豊かな風味を味わえる丸ぼうろやミルクキャラメル・チロルチョコなど大手メーカー商品とコラボした丸ぼうろなどの種類も販売しているため、初めて食べた人でもどこか懐かしさを感じる丸ぼうろの魅力を最大限に楽しんでみてはいかがでしょうか。