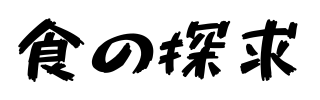夏の蒸し暑さを吹き飛ばすような鮮やかな赤色と酸味・甘味・旨味をバランス良く持つトマトは、夏野菜の代表格ともいえる野菜の1つで、みずみずしく爽やかな味わいやトマトに含まれる栄養素は夏バテ防止にも効果的です。生のままでも加熱しても幅広く使えるトマトですが、旬の時期や主要産地など身近であるが故に意外と知られていないことも多いのではないでしょうか。今回はそんな万能なトマトの特徴や旬の時期、栄養素などについて紹介していきたいと思います。
トマトとはー特徴ー
トマトは緑黄色野菜の一種で南米アンデス高原が原産地になります。メキシコに伝わった後、食用として栽培されるようになったため、メキシコ先住民の言葉で「膨らむ果実」を意味する「トマトゥル(tomatl)」という言葉がトマトの語源となっています。実はナス科に分類される野菜であることから和名では赤茄子とも呼ばれており、他にも唐柿(とうし)や蕃茄(ばんか)、英語ではLove Apple、イタリア語ではPomodoroなどいくつかの別名も存在しています。
古くからイタリアやアメリカ、中国、インドなどをはじめ世界中で愛され続けてきたトマトですが、日本には江戸時代に観賞用の植物として伝わったと言われています。鑑賞用から食用として栽培されるようなったのは明治時代に入ってから、さらに多くの人に食用として浸透するようになっていったのは昭和初期とされており、人気が高まるにつれて品種改良が進んでいきました。大きいものから小さいもの、色も赤色だけでなく黄色や緑などさまざまなトマトが作られるようになり、現在国内では300種類以上のトマトが各地で生産されているのです。大きさや色の違いによって酸味・甘味の強さ、食感、香り、水分量などの特徴も異なり、食べた時の印象や相性の良い調理方法も異なってきます。
トマトの一般的な旬の時期は6月~8月と言われていることから夏野菜のイメージが強いですが、品種が増えたことや露地栽培かハウス栽培かなど栽培方法の違いにより生産出来る期間が大幅に広がり、品種によっては旬の季節が春先や秋になるトマトも増えています。それだけでなく、夏場の水分量が多いトマトに比べると冬から春にかけて育った品種は寒い環境の中、時間をたっぷりと使って育つことで成分が凝縮され、濃厚で甘味や旨味を強く感じやすいトマトとなる傾向が強いため、近年は夏よりも春や秋に旬を迎える品種の方が美味しいと感じる人も増えているのです。本来は強い日差しと昼夜の寒暖差を好み、高温多湿を苦手とする野菜であることから夏場よりも少し早い初夏辺りが旬と言われていましたが、栽培方法の工夫や気候の違うさまざまな地域でも栽培されるようになったことで夏に限定せず、現在は1年を通して美味しいトマトが食べられるようになっています。
含まれる栄養素と摂取量
トマトにはさまざまな栄養素が含まれており、イタリアでは体調が優れない時などに薬膳料理として食べられている野菜でもあります。トマトの栄養はすごい!という声もよく聞きますが一体どのような栄養素が含まれているのでしょうか。
リコピン-トマト100gあたり約10mg
トマトの特徴である赤い色素成分のリコピンは強い抗酸化作用を持っており、活性酸素によるシミやしわの予防や老化防止、免疫力低下の改善、さらに動脈硬化や心筋梗塞など生活習慣病に繋がるリスクを抑制する効果も期待出来ます。
リコピンはカロテノイドという植物などが作り出す天然色素の総称で、赤の他にも黄色やオレンジなどの色をした野菜に含まれており、体内で生成することは出来ません。真っ赤になるほどリコピンの含有量が増えていくため、色の薄いトマトは風通しのよい常温で保管し追熟させることでより多くのリコピンが持つ効果を取り入れることが出来るでしょう。また、油に溶けやすい性質や加熱調理をすることで効率的に摂取しやすくなることから、油や火を使った調理方法がおすすめになります。すでに加工されたトマト製品や生でもオリーブオイルなどを一緒に使うことで吸収率がUPすると言われているため、取り入れ方が多様なのもトマトならではのメリットとなっています。
β-カロテン(ビタミンA)-トマト100gあたり540μg
リコピンと同じくカロテノイドの一種であるβ-カロテンも抗酸化作用を持っているため、酸化による老化防止などの効果を期待出来ますが、さらにβ-カロテンは体内で必要な分だけビタミンAに変換してくれることによって目や皮膚、粘膜などを健康に維持する役割や骨・細胞の発達を促進する効果も高めてくれます。これにより免疫機能の向上、視力低下や夜盲症、ドライアイの予防、老化・生活習慣病の予防、さらには新陳代謝の向上によってターンオーバーを促し、美肌効果や改善を期待することも出来るでしょう。
ビタミンC-トマト100gあたり約15mg
トマトにはβ-カロテンから作られるビタミンAの他にも、ビタミンB1やB2、ビタミンEなど多種類のビタミン群が含まれていますが、生のトマトに多く含まれているのがビタミンCです。もとから含まれるビタミン群の中では特に多く、風邪などの病原体に対する抵抗力の強化や疲労回復、免疫機能の向上など健康な身体を維持するために必要な役割を持っています。また、鉄分やカルシウムの吸収を促進する働きやメラニン色素の生成を抑制する働き、コラーゲンを生成するために必須な栄養素でもあるため、肌のハリや弾力を保ちながらシミ・そばかすの予防も期待することが出来ます。
その他
他にも、摂取しすぎたナトリウムを排出してむくみや高血圧の予防・改善に繋がるカリウム、腸内環境を整え便秘や肌トラブルの改善を促してくれる食物繊維などがトマトには含まれており、リコピンやβ-カロテン、ビタミン群の効果も合わせると健康と美肌に繋がる栄養素が非常に多く含まれているのです。
トマトにはさまざまな栄養素が含まれているだけでなくその栄養素のバランスがよいのも強みです。効果を知るとイタリアで薬膳料理として食べられているのも納得であり、日常的に取り入れていきたいと思う人も多いのではないでしょうか。では、トマトは1日にどれくらいの量を食べるのが適切なのでしょう。
1日の摂取量
トマトの1日の摂取量はMサイズ程度であれば2個が目安、ミニトマトの場合だと10~15個程度が目安となります。ちなみに、ミニトマトは普通のトマトよりも栄養価が高いと言われており、100gあたりだとミニトマトの方がβ-カロテンが約1.7倍、ビタミンCだと約2倍近くも多く含まれているのです。トマトもミニトマトも毎日食べるのは問題ありませんが、水分が多く食物繊維も豊富に含まれているため、1日の摂取目安量よりも多く食べてしまうと体が冷えてお腹をはじめとする体調不良を起こす、消化不良による便秘や下痢を引き起こす、トマトに含まれるシュウ酸によって尿路結石や胆石のリスクが生じるなど、逆効果となってしまうこともあるため、食べ過ぎには注意して下さい。
トマトの品種と分類
大きさの違いによる品種
大玉トマト
果重量100g以上のもの。大きいものだと200g以上のものもあり、日本の大玉トマトは桃色系の色が一般的となっています。
桃太郎
日本で最も多く生産されている品種になります。甘味と酸味のバランスが良く、果肉をしっかりと感じられるのが特徴で、完熟トマトの先駆けとなった生食から加熱調理まで幅広く使える品種です。完熟すると桃やブドウのような甘い香りを感じられるのも桃太郎トマトの特徴になります。
りんか409
高温下でも品質が安定していて病気に強く、耐虫性もあるため生産しやすい品種。糖度が高くコクがあり、肉厚でしっかりとした食感を持っていますが口に入れるととろけるような食感を感じられるのが特徴です。夏は酸味が強く、秋になるにつれて甘味が増す傾向が強いとされています。
ファースト
愛知県原産の伝統的な品種です。おしりの部分が尖っているのが大きな特徴で、完熟しても色づきが薄いトマトでもあるため、他の品種より個性的な見た目となっています。甘味と酸味のバランスも良く、薄い皮や実崩れしにくい・ゼリー状の部分が少ないことも特徴になります。
中玉トマト
果重量30~60g程度のもの。ミディトマトとも呼ばれています。大玉トマトとミニトマトの中間の大きさであり、食べきりサイズや糖度を高めたフルーツトマトなども中玉になるため、年々需要が高まっている種類でもあります。
フルティカ
丸く赤い見た目のフルティカは糖度が7~8度と高糖度で酸味が少なくコクがあり、滑らかな果肉が特徴。破裂しにくい品種であるため夏秋期の露地栽培にも向いており、薄い皮は口に残りにくいこともあって食べやすいとされています。
カンパリ
海外でも生産量が多く、日本には1990年にオランダから導入された世界的に有名な品種。甘味・酸味のバランスが良く硬めの皮が特徴で、リコピンやグルタミン酸の含有量が多いため、コクや旨味もしっかりと感じられます。
シンディスイート
病気に強く裂果しにくいため完熟した状態でも出荷することが可能です。色鮮やかでしっかりとした食感と甘く濃厚な味わいを楽しむことが出来ます。個体差によっては糖度が9度前後のものもあり、果物に近い甘さを感じられる品種でもあります。
ミニトマト
果重量10~30g程度のもの。チェリートマト呼ばれており、トマトの中では1番小さい種類になります。色は赤・黄色・オレンジ・緑とさまざまで丸や楕円形と形の種類も多いです。栄養価が高く全体的に糖度も高いため一般的なトマトよりも甘みや旨みを強く感じられます。
アイコ
細長い卵形をしたミニトマトの代表的な品種。酸味が控えめで糖度が高く肉厚、ゼリー部分も少ないため果汁が飛び散らず食べやすいとされています。イエローアイコやオレンジアイコ、プリンセスアイコなど品種も多く育てやすいことから家庭菜園でも人気の品種となっています。
オレンジパルチェ
鮮やかなオレンジ色の見た目が特徴のオレンジパルチェですが、平均糖度は15度以上とミニトマトの種類の中でも特に糖度が高く、メロンや桃など甘味の強い果物よりも甘いと言われている品種です。フルーティーなうえに独特の香りも持っているためデザートやおやつの代わりとして食べるのもおすすめです。
スイートミニイエロー
10~13度の糖度を持つスイートミニイエローは丸い形をした黄系ミニトマトの品種になります。フルーティーで酸味が少なくカロテンも多く含んでいるため、糖度の高さも合わせてジャムづくりにも向いている品種です。人によってはトロピカルフルーツのような味わいに感じるとも言われています。
サングリーン
完熟後も緑色をした品種であるため酸っぱいイメージを持たれがちですが、甘味が強くすっきりとした酸味を感じられる爽やかな風味のミニトマトです。肉厚でサクサクとした食感を持つことからサラダやピクルスなどの生食もおすすめですが、加熱すると旨味が増すためピザやパスタなどにも幅広く使えます。
フラガール
一口食べたら踊りたくなるほどの甘さと言われており、ねっとりとした甘さが特徴。皮は柔らかめで楕円形、デコボコとした少しいびつな形をしているのも特徴で、直売所でも入手困難な場合があるほど人気の高いミニトマトです。
大きさ以外の分け方
トマトは世界に10,000以上の種類があると言われており、日本だけでも300近い種類があります。基本的にトマトの種類は大きさで分けられることや判断することが多いですが、他にも色による分類や加工用か生食用かといった用途による分類、糖度を高めるなど栽培方法の違いによる分類などがあるため、さまざまな観点からトマトの種類を見てみると違った特徴や気づかなかった点などが分かり、よりトマトの美味しさや新たな魅力に気づきやすくなります。また、苦手意識が改善することなどにも繋がるかもしれません。
主要産地と旬の時期
トマトの栽培は日中が25℃~30℃、夜は10℃~15℃が適正と言われており、昼夜の温度差に加えて強い日光を浴びることが出来る環境こそが美味しいトマト作るポイントとなっています。そのため、年間を通して温暖な気候や多様な地形を持つ熊本県が日本一トマトの生産量が多い産地であり、その割合は全体の19%を占めています。他にも、北海道や愛知県、茨城県、栃木県などが上位を占めており、熊本県を含めたこの5県が日本のトマト生産量全体の約4割を占める主要産地になります。
露地栽培トマト
屋外の畑で育てられるトマトは気温や日光の強さなどが影響するため5月下旬~8月頃が旬の時期になります。昔は基本的には露地栽培でトマトが育てられていたため、初夏から夏にかけてしか流通しておらず、そのイメージから夏野菜として定着していきました。また、ミニトマトも基本的にはこの時期に旬を迎える野菜になります。
ハウス栽培
雨や風、害虫などの影響を受けにくいハウス栽培では2月~5月にかけて旬を迎えます。温度管理や水・肥料などの調整もしやすいことから現在はハウス栽培での生産が中心となっています。
夏秋トマト
熊本県の他、北海道や福島県、岐阜県など夏でも比較的涼しい地域で生産されているトマトであり、7月~11月が旬とされています。露地栽培を中心に自然に近い環境や標高の高い冷涼な地域で栽培されることが多く、冬春トマトと比較されやすい品種でもあります。トマトらしい酸味とさっぱりとした味わいが特徴で冬春よりも育つのが早いです。
冬春トマト
濃厚で甘味の強い冬春トマトは12月~6月頃が旬であり、早いものだと11月頃から収穫出来るものもあります。熊本県では年間生産量の約7割を冬春トマトが占めており、愛知県や栃木県でも作られています。時間をかけて育つため甘味や旨味が凝縮してコクが生まれ、日持ちが良いのも特徴です。
産地や作られている時期によって味や食感など異なる特徴を持つトマトが多いため、購入する際には地域や購入する時期にも注目するとよりトマトの美味しさを実感しやすくなるでしょう。
食べ方・調理方法
トマトは多様な種類があるため、それぞれの特徴にあった食べ方をするのが1番美味しく食べられます。甘味が強いものや食感が良いものはサラダやマリネ、ピクルスなど生食で、酸味が強いものや熱を加えることで旨味が増すものはパスタやトマトソースに加工して使うなど調理方法1つで全く違った美味しさを味わうことが出来ますが、栄養素の特徴によっても食べ方や調理方法が異なってくるため、トマトの効果をより効率的に摂取出来る方法をご紹介します。
ビタミンCを摂取したい場合
トマトに含まれるビタミンCは熱に弱い性質を持っているため、ビタミンCを重視する場合は生のまま食べるのがおすすめです。また、皮にはリコピンやβ-カロテンも多く含まれており、油との相性も良いことから、オリーブオイルをかけるサラダやマリネなどにして皮ごと食べるとより効率的にトマトに含まれるビタミンCを摂取することが出来ます。ただし、皮は消化吸収されにくいことから、胃腸の弱い人は食べる量に気をつけないと体調不良を起こす可能性があります。そのため、皮が柔らかく栄養価も高いミニトマトを積極的に取り入れるのもおすすめです。加熱する場合は、出来るだけ加熱時間を短くすることでビタミンCの損失を抑えることが出来るため、調理するタイミングや加熱方法を工夫するのも良いでしょう。
おすすめ調理方法
- そのまま食べる
- サラダ
- マリネ
- カプレーゼ
- ピクルス
- うどん・そうめん・冷静パスタなどの具材
リコピンを摂取したい場合
油に溶けやすい性質を持っているリコピンを積極的に摂取したい場合は加熱調理するのがおすすめです。トマトは加熱すると細胞壁が壊れてリコピンが体内で吸収されやすくなり、旨味も増すため、焼く・炒める・煮る・蒸すなど取り入れやすい方法で取り入れるのが良いでしょう。また、トマトジュースやケチャップ、トマトソースなどすでに加工されているものは、元々リコピンの含有量が多い品種で作られていることが多く、加熱調理することでさらに効果を発揮するため、手軽さを求めるのであれば加工品を使うのもおすすめです。さらにリコピンは朝に摂取すると1番吸収率が高いという研究結果が出ていることから、朝食時にトマトジュースを取り入れるのも良いでしょう。
おすすめ調理方法
- グリル
- パスタ
- ピザ
- トマト煮込み
- レンジ蒸し
- 串焼き
- スープ
美味しいトマトの見分け方
1年を通してスーパーで簡単に購入出来るトマトですが、より新鮮で美味しいトマトを選ぶにはどのようなポイントに注目したらよいのでしょうか。
- 全体的に赤くムラがないもの
- 実が締まって弾力があり、ハリやツヤを感じられるもの
- ヘタがピンとして濃い緑色をしているもの
- ずっしりと重みを感じられるもの
- おしりの部分から放射状に白い線(スターマーク)が伸びているもの
実やヘタの状態や傷などポイントを見極めることで美味しく完熟したトマトを選ぶことが出来るため、購入する際にはぜひ注目してみて下さい。
トマトの保存方法
冷蔵保存
トマトの保存に適した温度は10℃前後と言われているため、基本的には冷蔵庫で保存するのが良いです。より長持ちさせたい場合は1つずつキッチンペーパーで包んでヘタ側を下にし、保存用ポリ袋に入れて野菜室で保存すれば7~10日ほど保存することが出来ます。カットして余ったトマトはラップをすれば冷蔵庫で保存出来ますが、水分が出て傷みやすくなるためなるべく早めに消費した方がよいでしょう。
ミニトマトの場合は、雑菌が繁殖しやすいヘタを取って水洗いし、キッチンペーパで水気を拭き取ります。保存用ポリ袋でも問題ありませんが実割れしやすいため、保存容器に入れて野菜室で保存する方が長持ちしやすくなります。保存期間はトマトと同じく7~10日程度です。
常温保存
購入した時の状態によって保存方法を変えることも可能になります。まだ実が固く青いなど完熟していない場合は常温で保存して追熟させるのがおすすめです。
冷蔵保存と同じくトマトをキッチンペーパ-で包んだ後、そのままヘタ側を下にして15~25℃ほどの冷暗所で2~3日保存します。完熟後はポリ袋に入れて野菜室で保存すれば同じく7~10日ほど保存することが可能です。
冷凍保存
トマトは冷凍することも可能であるため、大量購入した場合や使いきれず余ってしまった場合には冷凍庫で長期間保存するのもおすすめです。
丸ごと冷凍する場合は、洗ったトマトの水気を拭き取り包丁でヘタを取り除きます。冷凍用保存袋にヘタがあった部分を下向きにして入れて空気を抜き、冷凍庫で保存します。カットしたトマトの場合は、余分な水分を拭き取りトマトが重ならないよう冷凍用袋に入れるのがコツです。ミニトマトも同様にヘタを取って洗い、水気を拭き取った後、冷凍用保存袋に入れて冷凍します。
冷凍した場合、約1ヶ月間保存することが可能となり、さらに丸ごと冷凍したトマトは解凍時に水にさらすと簡単に皮がむけるので、皮剥きが必要なレシピには有効活用することが出来ます。ただし、冷凍してしまうとトマト本来の食感は失われてしまうため、どのタイプでもスープやトマトソースなど加熱調理に使うのが良いでしょう。
トマトに関連したイベントなど
スペイン王国バレンシア州ブニョールではラ・トマティーナと呼ばれる世界的にも有名な「トマト祭り」が毎年8月に行われています。大量のトマトを投げ合い、人も街も真っ赤に染まるトマト祭りには地元だけでなく各国から多くの観光客が訪れる人気のイベントとなっていますが、日本ではトマトに関連したイベントは行われているのでしょうか。
ひのトマトフェス
東京都日野市で生産されているトマトの魅力を広めるために毎年行われているイベントが”ひのトマトフェス”になります。「トマト農家を応援したい!地域の農業を盛り上げたい!」という想いから日野市の農家と飲食店が手を組んで始まったこのイベントでは、新鮮なトマトの直売や試食販売などはもちろんのこと、ラーメンやカレー、パン、ケーキなどトマトを使ったオリジナルフードやトマトのクラフトビール・オリジナルカクテルなど、ひのトマトフェスでしか味わえないメニューも多数用意しています。他にも、ハンドメイド作品の販売やダンスステージ・音楽演奏・クイズ大会など盛りだくさんで、トマトを身近に感じながらも幅広く楽しめるフェス形式のイベントとなっています。
やつしろTOMATOフェスタ
日本一冬トマトの生産量を誇る熊本県八代市で毎年行われている、国内最大級のトマトイベントが“やつしろTOMATOフェスタ”です。八代市内にある飲食店で八代産トマトを使ったメニューを食べてシールを集めるスタンプラリー形式のイベントになります。イタリアン料理店や中華料理店、居酒屋、カフェ、割烹、うなぎ屋などジャンルの異なる30店舗近い飲食店で対象メニューを食べると1枚シールがもらえ、シールの枚数によって抽選で当たる八代市の特産品など豪華商品に応募することが可能です。美味しい八代産のトマトを使った絶品メニューを食べて魅力を発信するやつしろTOMATOフェスタは2012年から始まり、10年以上も続くトマトの祭典として親しまれています。
不思議の畑とトマトの樹
ケチャップやトマトジュースで有名なカゴメは野菜を育てる過程や畑などへの関心、自然に対する好奇心や感謝などを高めるため、2022年から“不思議の畑とトマトの樹”という体験型イベントを開催しています。長野県諏訪郡富士見町にある「カゴメ野菜生活ファーム冨士見」を中心に、子供たちが参加しやすい商業施設を会場にしており、野菜についてのクイズやARの体験、オリジナルストーリーの上映、さらにはミニトマトの収穫体験など、実際に手で触れて考える新しい形のイベントとなっています。その年によって会場や内容も変わり、子供も大人も楽しみながら学ぶことが出来るイベントとなっているため、近場で開催される際にはぜひ一度足を運んでもらいたいです。
この他にも、年々トマトに関連するイベントやフェスは増えており、トマトの人気の高さと万能さ、そしてその魅力を実感することが出来ます。栄養価が高く、身体に良い効果をたくさんもたらしてくれる野菜の1つであるため、ぜひ日常的に美味しくトマトを取り入れて、健康や美容効果をしっかり体感してみて下さい。