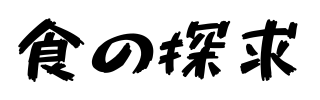瀬戸内海と宇和海に面した愛媛県は海だけでなく西日本最高峰の石鎚山もあり、豊かな自然に囲まれた気候の穏やかな県です。また、道後温泉や松山城といった古い歴史を持つ観光地もたくさんあり、旅行地としても人気の高い愛媛県では全国的にも親しまれている有名な特産物やグルメがいくつもあります。今回は愛媛県を訪れる際にはチェックしておきたい代表的な特産物やグルメについて紹介したいと思います。
柑橘類
愛媛県といえばみかん、みかんといえば愛媛県というイメージも強いほど県内ではみかんの生産が盛んに行われており、その生産量は常に上位3県に入るほど多く、和歌山県と静岡県と合わせた3県で全国の約6割を占めています。和歌山県・静岡県も生産が盛んでみかんをはじめとする多種類の“柑橘類”を栽培していますが、愛媛県の凄いところはみかんの他にいよかんやポンカン、甘夏といった馴染み深い種類からはるみ・せとか・はれひめなどの品種改良によって優れた風味を持つもの、そして紅まどんなや紅かんぺいといった愛媛県オリジナル品種まで合わせると約40品種を栽培しており、その品種の多さは日本一となっています。品種が多いため、甘さと酸味の強さやバランスが異なるものはもちろん、シャキッとした食感やゼリーのような口当たりの優しいものなど食感に特徴を感じられる品種も多く、旬の時期も違うことから1年を通して多種多様の柑橘類を楽しむことが出来るのが愛媛県の強みです。そのため、生産量・栽培品種の多さから別名で「かんきつ王国」とも呼ばれています。
愛媛県で柑橘の栽培がはじまったのは江戸時代の終わり頃、伊勢参りや四国巡礼をした際に手に入れたみかんの苗を宇和島に植えたのが最初と言われています。穏やかで晴れの日が多く、平均気温も15℃以上と温暖な気候の愛媛県は、水はけがよく、潮風によって海のミネラルを含んだ土壌やみかんが成長するために重要となる8月~10月の日照時間が長いことなど、美味しいみかんを栽培するために必要な環境と条件が揃っていたこともあり、明治時代以降はみかんを扱う農家が増えていきました。県内のみかん畑は山を切り開いたところに石を積み上げて段になるように作られていることから木々同士が重なりにくく、太陽の光をたくさん浴びることが出来ます。また、愛媛県のなかでもみかん産地として有名な宇和島や瀬戸内の島々の立地は、空からの光だけでなく海に反射した反射光と海沿いに見られる石垣からの照り返しも加わった「三つの太陽」の力によって通常よりも多くの太陽を浴びて育っています。さらに、雨が多い地域や水はけが悪く土に水分が残ってしまう土壌では木が余分な水分を吸い上げ、みかんの味を薄めてしまう原因になってしまいますが、愛媛県は降雨量が少なく水はけのよい土壌であるため旨みが逃げず、ジューシーで美味しいみかんを育てることが出来るのです。こうした特徴のある段々畑や三つの太陽の力、管理の難しい水分量が愛媛県産のみかんの質を上げており、そして何よりも手間をかけて育ててきた農家の人々の地道な努力と長年に渡る品種改良によって多種多様の美味しい柑橘類を栽培することに繋がっています。
県内で作られている柑橘類の種類の多さはもちろんですが、その柑橘類を使った加工品が多いのも愛媛県の大きな特徴です。定番のジュースやジャム、ゼリーやお菓子などそれぞれの中でも種類があり、同じ商品で味の違いを食べ比べることが出来る商品も多くあります。また、無農薬みかんを塩で漬けこんだ塩みかんや柑橘の香りを感じられる醤油・ポン酢・ドレッシング、皮をそのまま使ったパウダーやペーストなど調味料として使えるものも多く、料理やお菓子に使えば一気に爽やかな香りとさっぱりとした味わいをプラスすることが可能です。さらに県内にはクラフトビールを醸造するブルワリーが多数あり、柑橘の果汁やオレンジピールを使ったビールも続々と販売されているため注目度が高く、フルーティーな香りや柑橘の甘み、さっぱりとした味わいはビール好きの人からビールが苦手な人まで男女年齢問わずに幅広く好まれています。他にもリキュールや果実酒、みかんを使った梅酒などお酒のジャンルも多く、贈り物やお土産にも重宝されており、お酒に限らず他県では見かけない商品の扱いがあるのもかんきつ王国と呼ばれる愛媛県だからこその品揃えとなるのでしょう。そのため、愛媛県に訪れた際にはぜひ、太陽をたくさん浴びて育ったみかんをはじめとする多種類の柑橘を楽しむのと一緒にお気に入りの加工品を探してみて下さい。また、生のまま食べる機会があれば愛媛県オリジナルの品種もおすすめですが、他県でも生産されている定番の品種こそ風味の違いを感じやすいため、さまざまな品種を食べて全国トップレベルの美味しさと種類の多さを実感してみて下さい。
鯛料理
愛媛県の特産物であり県の魚にも選ばれているのが“鯛(真鯛)”です。県の西側には宇和海が広がっており、太平洋から流れ込む黒潮によって栄養やミネラルが豊富で、脂ののった美味しい鯛がたくさん漁獲されるため、古くから郷土料理にも多く使われてきました。また、愛媛県では鯛の養殖にも力を入れており、人口ふ化から育てた親魚の卵を使って完全養殖を確立させていることに加えて、複雑な入江のリアス式海岸が養殖場に適していること、設備や飼育の工夫によって養殖環境も整っていることなどから、天然物にも負けないほど品質の高い鯛を生産することが出来ています。さらに、同じく特産物であるみかんを加工した際に発生する皮などを餌に混ぜて養殖する「みかん鯛」の評価も高く、みかんの皮に含まれるポリフェノールやリモネンという成分によって魚特有の臭みを抑えるだけでなく、ほのかに柑橘系の香りもするため魚が苦手な人でも食べやすいと言われています。そのため、愛媛県の鯛は天然・養殖どちらも日本一の生産量を誇っており、近所のスーパーや鮮魚店でも手軽に購入出来る魚の1つであることが身近で親しまれている理由となっているのです。
県内には鯛を使った郷土料理がいくつかあり、そうめんに一尾丸ごと煮付けた鯛をトッピングした「鯛そうめん」も有名ですが、特に人気が高いのが“鯛めし”です。隣県である徳島県でも食べられていますが発祥は愛媛県であり、その歴史も非常に古く、弥生時代、神功皇后(しんぐうこうごう)が朝鮮へ出陣する際に戦勝祈願として食べられていたと言われています。土鍋にお米と出汁、調味料、さらに鯛を一尾丸ごと入れて一緒に炊き込み、炊き上がってから身をほぐしてごはんと混ぜて食べるのが一般的で、今治がある東予地方や松山がある中予地方を中心に県内の広い地域で食べられています。鯛の旨みをしっかり感じられるのが特徴で、お店によっては切った鯛を釜めしや1人用の土鍋に入れて食べやすいサイズで提供することやほぐした鯛の身と出汁をかけてお茶漬けにして提供するなど、状況によって食べ方や提供の仕方が変わることもあります。また、徳島県では事前に鯛を焼いて焦げ目をつけた状態でごはんと一緒に炊きますが、愛媛県では焼かずに生のままごはんと一緒に炊くことが多いという違いもみられます。
さらにおもしろいのが、愛媛県には鯛めしがもう1種類あるということです。一般的な炊き込んで作る鯛めしに対して、宇和島がある南予地方や西予地方では鯛の切り身を醤油やみりんなどの特性のタレに漬け込んだ「漬け丼」を鯛めしとして食べる習慣があり、別名で「宇和島鯛めし」とも呼ばれています。県の南部は九州に近く、古くから大分県や宮崎県沖まで漁をすることも多かったため、火が使えない船上でも簡単に作れる料理として漁師たちが食べるようになったのがはじまりと言われています。しかし、この他にも宇和海の日振島を拠点にしていた伊予水軍が船上で酒盛りをしていた際、ごはんと刺身、醤油を混ぜ合わせて食べたのがはじまりとも言われており、発祥には諸説あるようですがいずれにしても、どちらとも火が使えない海の船上だったからこそ誕生した食べ方と言えるでしょう。また、宇和島鯛めしは卵黄を使うのが特徴で、お店や作る人によって特製のタレに卵黄を混ぜて漬け込むタイプと最後に卵黄を落としてトッピングとして使うタイプと分かれるようです。この卵黄のとろみがタレに漬かった鯛とよく絡み、風味や食感を引き立たせてくれるため、炊き込む鯛めしとはまったく違った美味しさを味わうことが出来ます。地域によって違う形で親しまれてきた2種類の鯛めしですが、現在は両方を扱う店舗も増えており、違いを食べ比べることも可能となっています。他にも県内では、鯛しゃぶや刺身といった定番の食べ方から地元の小学生が考案した鯛カツ丼、鯛の切り身を竜田揚げやフライにして具材に使ったハンバーガーなどさまざまな形で鯛料理を食べることが出来るため、愛媛県で獲れる美味しく質の高い鯛を思う存分堪能してみてはいかがでしょうか。
じゃこ天
宇和島市がある南予地方の郷土料理でありながらも、県内で知らない人はいないほど認知度が高くソウルフードとなっているのが“じゃこ天”です。練り製品の一種であるじゃこ天は小魚を丸ごとすりつぶして作られており、魚の骨や皮も一緒にすり身にしているため一般的な練り製品に比べると味も色も濃く、独特の食感と弾力、魚の旨みをしっかり感じられるのが大きな特徴になります。また、ヘルシーであるうえに牛乳の2倍以上のカルシウムをはじめ、ミネラル、DHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエンサン)といった栄養素も豊富に含まれていることから、脳細胞生成の促進や認知症の改善、中性脂肪の減少、血液の改善など生活習慣病の予防や改善といった効果を期待することが出来るため、健康や美容の意識が高い人からの注目度も高いです。宇和島では昔から油で揚げた魚のすり身を「天ぷら」、さらに皮や骨まで入ったすり身を使う場合「皮天ぷら」と呼んで親しまれてきたため、野菜や魚介類を具材にした揚げ料理を天ぷらとイメージすることが多いなか、県内ではじゃこ天や練り製品を指すことの方が強く、愛媛県ならではの特徴にもなっています。
宇和島でかまぼこなどの練り製品を作り始めたのは江戸時代と言われており、初代宇和島藩主の伊達秀宗が仙台から蒲鉾職人を連れてきたのがはじまりとされていますが、海が近い立地であったためそれ以前からかまぼこを作っていた可能性は高いそうです。じゃこ天は雑魚という一匹では売り物にならないさまざまな魚を美味しく食べてもらいたいと言う母親たちの思いから、南予地方の家庭で作られるようになった家庭料理であり、広まるにつれて魚屋やかまぼこ店などでも製造・販売するようになっていきました。そのため、名前の由来としては雑魚を使っていたことから「ざこ天」と呼ばれるようになり、少しずつ変化してじゃこ天になったと言う説が有力です。主原料にホタルジャコという魚を使っているためじゃこ天と呼ばれるようになったと言う説もありますが、そもそもホタルジャコが雑魚からついた名前であるため、根源の由来は同じとなっています。また、使う雑魚の種類や配分によって出来上がったじゃこ天の風味や弾力などが変わることから、作る職人やメーカーによっても特徴が異なり、行きつけの店舗や贔屓にしている商品がある地元民も多いです。なかには開店前から行列になるほどの人気店もあり、じゃこ天をはじめとする手作りの練り製品が数時間で売り切れてしまうほどの人気っぷりを窺うことが出来ます。
じゃこ天は楽しみ方のバリエーションが豊富であるのも広く親しまれている理由の1つとなっています。じゃこ天本来の風味を最大限に楽しむのであればそのまま食べるのがおすすめで、フライパンや網、トースターなどで軽くあぶっておくと香ばしさもアップします。お好みに合わせて醤油やポン酢、大根おろし・生姜・すだちなどの薬味を用意すれば、おやつやおかず、お酒のつまみとしてもピッタリです。他にも、雑魚の旨みをしっかり感じられることからうどん・そばのトッピング、炊き込みごはん・和え物・サンドイッチなどの具材としても幅広く使うことが可能で、特に発祥の南予地方では日々の食卓には欠かせない食材として親しまれています。そのため「天ぷらカレー」としてカレーの具材である肉の代わりにじゃこ天を使うなど、珍しい使い方をすることも多く、長年愛されてきたソウルフードだからこそさまざまな食べ方や楽しみ方が生まれているのです。地元の方はもちろんですが、観光客にもじゃこ天の人気は高いため、愛媛県を訪れた際やじゃこ天を食べたことがないという人はぜひ、歴史あるじゃこ天や天ぷらと呼ばれる練り製品を食べて豊かな風味と食感を楽しんでもらいたいです。また、じゃこ天の生地にたまねぎや人参などを加えてパン粉をつけた「じゃこカツ」も人気があり、じゃこ天とは違った美味しさを味わうことが出来るため、居酒屋などで見かけた際には食べ比べてみるのもおすすめです。
鍋焼きうどん
寒い冬の日に食べたくなる“鍋焼きうどん”は煮込みうどんの一種であり、1人用の土鍋やアルミ鍋を使って提供されます。冬になると使い捨てのアルミ鍋に入った市販の商品も販売されているため、地域問わず身近な食べ物ではありますが、愛媛県松山市では古くからソウルフードとして親しまれており、冬場だけでなく1年を通して食べることが出来るのです。松山市を中心に食べられている鍋焼きうどんは、土鍋で提供する店舗もありますが「アルミ鍋」を使うのが定番で、見慣れた使い捨てタイプのものではなくレトロ感溢れる調理用の小型アルミ鍋を使っているのが特徴になります。中身は甘めの優しい出汁と柔らかいうどんを使うことが共通しており、エビ天などの天ぷらよりも甘めに味付けをした牛肉とネギ、かまぼこ・じゃこ天・なるとといった練り物がトッピングされているのが松山流とされています。そのため、うどん文化が根付いている香川県のコシが強く、塩味といりこなどの旨みを感じられるうどんとは一味違った味わいや食感を楽しむことが出来るでしょう。また、コシの少ないうどんは松山の煮込みうどんならではの特徴ですが、その柔らかさから「腰抜けうどん」と呼ばれることもあります。
松山市で鍋焼きうどんが誕生したのは戦後間もない頃、空襲の被害が大きかった市街地は大半が焼失してしまい、その中でも温かい食べ物を食べてもらいたいという思いから、戦前に料理屋を営んでいた3人の娘を持つ女性が屋台でうどんを提供し始めたのがはじまりとなっています。食料を確保するのも難しいなかで手に入れやすかったのがうどんであったことと、冷めにくいという特性を持っていたことがうどん店をはじめたきっかけとなっており、その後は「ことり」という店舗を構えて三姉妹やその家族が経営を引き継ぎ、今でも松山では有名な老舗として親しまれています。また戦後、同じ時期に鍋焼きうどんを提供し始めた「アサヒ」も地元民や観光客からの人気が高い老舗であり、2大巨頭として松山の鍋焼きうどんをけん引し続けています。ちなみにアルミ製の鍋を使い始めたのはアサヒとされており、物資が限られていた中でも丈夫で長持ちしやすく、熱伝導率が高いことから提供するまでの時短に繋がるという理由から使うようになったと言われています。
うどんの柔らかさと同じく特徴となっている甘めの味つけは、予想以上に甘く、初めて食べる人の中には驚く人も少なくありません。これは戦後、貴重品であった砂糖の甘い味つけがご馳走とされていた時代があり、鍋焼きうどんの味つけも甘めになったと言う説がありますが、実際には愛媛県で作られている醤油自体が甘めの作りであるのが大きく影響しているようです。また、お店によっては砂糖やみりんを使っている可能性もありますが、椎茸や昆布などのダシから出る旨みや甘みも強いことから、全体的にくどさやしつこさはなく、柔らかいうどんや具材との相性が良いのも大きな魅力となっています。現在は2大巨頭の老舗と合わせて市内のうどん屋や食堂、茶屋など1年を通して鍋焼きうどんを提供している飲食店が多いため、季節問わずに気軽に食べることが出来ます。さらに、ほとんどのお店にはサブメニューとしていなりずしを置いていることが多く、鍋焼きうどんと一緒に注文するのが定番にもなっているため、うどんの特徴の違いを味わいながら各店舗のいなりずしにも注目してみて下さい。
タルト
“タルト”といえば、クッキー生地やパイ生地の器にフルーツとクリームをたっぷり使ったケーキをイメージしますが、愛媛県ではカステラ生地にあんこを巻いたロールケーキ状の和菓子のことを表すことが多く、県を代表する銘菓や伝統菓子としても知られています。バターの風味とサクッとした食感が特徴の洋菓子のタルトとは一転し、カステラ生地のしっとりとした食感とあんこの風味が絶品で「の」のような形をした断面の美しさも相まって、愛媛県や四国を訪れた際の定番のお土産としての人気も高いです。現在は県外の物産展やアンテナショップなどでは取り扱われていることが多く、さらに品揃えが豊富なスーパーなどでも見かける機会が増えているほど全国的にも身近なお菓子になりつつあるのです。新鮮な卵を使って丁寧に焼き上げられているからこそ、口当たりが滑らかな生地に仕上がり、美味しさの重要なカギとなっていますが、あんこを乗せた後の巻く工程も職人によって丁寧に手作業で行っているメーカーが多く、定着するように寝かせていることが美しさと一体感を産み、一貫したこだわりと丁寧な作業工程が人気の秘訣に繋がっています。
愛媛県でタルトが誕生したのは江戸時代にまで遡り、現在の松山で発祥したとされています。1647年にポルトガル船が長崎へ入港したことを聞きつけた松山藩主・松平定行(久松家初代)が海上警備のために訪れた際、柑橘系のジャムをカステラで巻いた南蛮菓子に出会い、松山に製法を持ち帰ったのがきっかけとなったそうです。松山に持ち帰った後は独自に改良し、日本らしさとして和菓子の要素を取り入れたことで現在のようなあんこを巻いた形になったとされています。その際に、原形となった南蛮菓子には柑橘系のジャムが使われていたこと、さらに柚子が四国の特産物であったことも重なり、あんこのなかに柚子をアクセントとして加えるようになったため、現在もスタンダードタイプのタルトからはほのかに柚子の香りが感じられるのも特徴となっています。ちなみにタルトという名前は、オランダ語でケーキを意味する「taart」とポルトガル語でロールケーキを意味する「torta」から来ている2つの説が有力とされていますが、どちらの方が信憑性が高いかは不明です。タルトの誕生後は久松家の家伝となりましたが、明治時代以降に松山の製菓業に技術が広まり、広く愛されるお菓子へと成長していきました。現在は、有名メーカー6社を中心に多数のメーカーでタルトが作られており、栗がまるごと入ったタルトやいよかんの羊羹が入っているもの、1本売りから切られているもの、ひとくちサイズのもの、さらには抹茶や甘夏みかん、桜、チョコレート、鳴門金時、いちごといった季節を感じられる限定の風味などサイズや風味を合わせると多数のタルトが販売されています。製造メーカーによっても味わいや食感が少しずつ違うため、限定風味と一緒にスタンダードのタルトの食べ比べをするのも楽しいかもしれません。