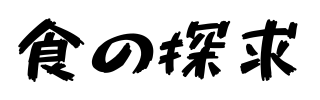美味しいステーキを食べたいと思っていても家では上手に焼けず失敗してしまった・失敗するくらいなら食べに行った方が美味しいなんて思ったことはありませんか。肉の質やランクが違うから仕方がない、プロじゃないから失敗するなんて思ってしまう人も多いステーキですが、実はコツやポイントを掴めばスーパーで購入した肉でもとっても簡単に美味しいステーキを焼くことが出来てしまうのです。今回はそんなステーキを家庭でも美味しく焼くコツやポイントを紹介していきます。
家でステーキを美味しく焼く方法
ステーキはとってもシンプルな肉料理であるため、上手に焼かないとパサついてしまう、硬くて噛み切れない、肉汁を感じられないといった残念な印象の仕上がりになりやすいです。しかし、焼き方を変えるだけで肉の質やランクは関係なく柔らかく美味しいステーキに仕上げることが出来ます。家で焼く時のポイントとしては
- 肉の厚みと調理前の温度
- 火の強さ・加熱時間
- 筋切りをする・余分な脂肪は切り落とす
- 塩コショウは直前にする
肉は加熱をすることでたんぱく質が固まり、歯で噛み切ることが出来るようになります。しかし、加熱をしすぎてしまうと筋肉が縮んで硬くなり、肉汁も外に流れ出てしまうことで肉質が硬くパサついた食感になってしまうのです。そのため、特に火加減や加熱時間が重要であり、これを上手に調整することで安い肉でも噛み切れる柔らくジューシーなステーキを焼くことが出来ます。
実は使う肉の厚みによって加熱する時間などを変えた方が失敗しづらく美味しいステーキを焼くことが出来ますが、今回はスーパーでよく販売されている2cm以下の厚みの少ない肉の焼き方に注目してポイントと一緒に紹介していきますね。
厚み2cm以下のステーキの焼き方
1.冷蔵庫から取り出した肉に下処理をして冷たい状態で焼く
2.弱火~弱めの中火で焼いていく
1分くらいして焼き色が付いたら裏面も同じように焼きます。
3.両面に焼き色が付いたら取り出して5分ほど休ませる
休ませている間に同じフライパンでソースやつけ合わせを作ります。この時に休ませている肉から汁が出ている場合、血ではなく旨み成分であるためソースに加えると旨みやコクが出るため余すことなく使いましょう。
4.休ませた肉にさらに焼き色を付けていく
この時の肉はまだレアの状態であるため、休ませた肉の表面の水分を軽くキッチンペーパーで拭き取り、油を入れたフライパンに肉を入れ中火でさらに30秒~1分を目安にカリっと焼いていきます。
ただし、バターを使う場合は中まで火を通してから休ませた方がバターと肉の旨みをソースに活かすことが出来るため、冷蔵庫から出した肉を弱火で30秒ほど軽く両面を焼いたらそのまま1分ずつ加熱し、さらにひっくり返して1分ずつの合計4分加熱してから取り出して休ませておくのがよいです。
焼く前の下準備
肉の赤身と脂身の間にある筋が太い場合は、事前に包丁で2~3か所切れ目を入れて筋切りをしておきます。太い筋が入った状態で焼いてしまうと、加熱による縮みから肉自体が反り返ってしまうため筋切りをしておくと防ぐことが出来ます。ただし、細かい筋まで切れ目を入れる必要はなく、太い筋のみに切れ目を入れておけば問題ありません。
また、肉を焼いたフライパンでソースを使う場合は、肉の周りに付いている脂身を切り落として焼く前の油分として使うとソースを作る際にも旨みやコクに繋がります。ただし、必ず取らなければならないものではないため、好みやソースを作るか否かなどの作る内容や状況によって切り落とすようにして下さい。
下味を付けることも焼く前の大切な下準備ですが、ここでも重要なポイントがあります。それは焼く直前に塩コショウを振るということです。あらかじめ下味を付けておいた方が下味が馴染むのではないかと思いますが、塩は水分を表面に引き出す力があるため、下味を付けてから焼くまでに時間があると肉の水分と一緒に旨みが表面に引き出され外に流れ出てしまいます。そのため、焼く直前に塩コショウをすることがポイントとなります。また、塩コショウをする前に肉の表面が水っぽい場合は、キッチンペーパーで軽く取っておくと加熱した時に油ハネが起きにくく、臭みも取れるため取り除いておきましょう。
肉の厚み・調理前の温度
冷蔵庫で保存している肉は、使う時に冷たいままだと加熱するのに時間がかかり、中までしっかり熱が届かず生焼けになりやすいです。そのため、焼き始める30分~1時間前に冷蔵庫から出して“常温に戻しておきましょう”という説明をよく見ますが、ここに1つ気をつけて欲しいポイントがあります。それは、使う肉の厚みです。
厚みが2~3㎝以上ある肉は火が通りにくいことから、事前に常温に戻すことで厚みがあっても熱が伝わりやすく生焼けを防ぐことが出来ます。しかし、スーパーなどで販売している肉は厚みが1.5~2㎝以下のものが多く、厚みが少ない肉を常温に戻してから焼いてしまうと火加減によってはあっという間に中まで熱が伝わり、加熱のし過ぎにより肉質が硬くなってしまう・パサつくといった失敗に繋がります。
そのため、使う肉の厚みによって常温に戻すのか冷たいまま使うのかが変わり、このポイントを押さえておくことで失敗しにくくなります。厚みが2~3cm以上ある肉の場合は事前に常温に戻した方がよいですが、スーパーなどで手軽に手に入れられる肉は厚みが少ないため常温に戻さず冷蔵庫から取り出した冷たい状態のまま使うのがよいです。また、肉の厚みが統一でないと熱の伝わり方が部分的に変わってしまうため、出来るだけ平らで厚みに片寄りがない肉を選ぶのも失敗を防ぐポイントになります。
冷凍している肉は必ず事前に解凍しておきましょう。流水やレンジなどを使って急速に解凍してしまうとドリップと呼ばれる肉汁が出やすくなってしまうため、解凍する時は冷蔵庫で時間をかけて解凍するのがよいです。
火の強さ・加熱時間
肉の厚みによって火の強さや加熱時間も変わってきますが、今回のような厚みの少ない肉の場合、熱が伝わりやすいことから“弱火~弱めの中火”で表面に焼き色を付け一度肉を休ませることで加熱のしすぎを防ぎ、肉汁を内側に留めて旨みを流れ出させないようにします。
強火で一気に加熱してしまうと表面に焼き色がつく前に内部にも熱が伝わり、焼き色がつく頃には硬くなってしまうだけでなく肉汁も外に流れ出てしまいます。これが常温だとさらに短時間で熱が伝わってしまうため、低温調理の要領で冷たい状態から火を少しずつ入れていくことで柔らかく焼き上げることが出来きるのです。
また、休ませる時にアルミホイルで包む方法もありますが、厚みが少ない場合は熱が伝わりすぎてしまうため、何もしないでパッドなどの上において休ませるのがよいでしょう。
今回は、手軽に手に入れられる厚みの少ない肉を使ったステーキの焼き方について紹介しました。ただし、使うフライパンや肉の厚み、焼き加減の好みによっては加熱時間を調整する必要があります。また、シンプルが故に非常に奥深く、プロでも人によって焼き方や取り入れる方法がいくつもあるため、他の方法と焼き具合や仕上がりの違いを比べて自分のやりやすい方法を探してみるのもおもしろいです。
ちなみに、肉についているランクは生産性の高さや霜降り度合いによりつけられており、アルファベットと数字を用いたランク付けは日本独自のものになります。A5 =美味しい肉というイメージを持ちやすいですが、実際には生産性が高く霜降り度合いも高い肉にA5がつけられており、味が美味しいという理由ではランク付けされていません。ランクや質がよくても焼き方を失敗してしまえば、パサつきが出て硬くなり、反対に価格が安くても上手に焼けば値段以上の美味しさを味わうことが出来るのです。ポイントやコツを押さえて、家でも美味しいステーキを焼いて普段だけでなく誕生日などの特別な日にも活かしてみて下さいね。