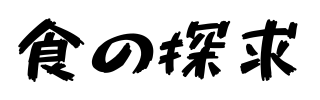熊本県は世界最大級のカルデラ(陥没地)を持つ阿蘇山や歴史を感じられる熊本城、天草諸島などがある自然豊かな県です。また、海と山に囲まれ夏と冬の寒暖差が大きいことや立地、縁のある歴史上人物の影響などから熊本県ならではの食文化が根付いており、大きな特徴にもなっています。今回はそんな熊本県の全国でも有名な特産品や郷土料理について紹介していきたいと思います。
馬肉料理
各都道府県ではブランド畜産物と呼ばれる牛肉や豚肉、地鶏を生産していることが多く、その質の高さから県民をはじめ観光客などにもご当地グルメやギフトとしての人気が高く親しまれています。熊本県でも「くまもとあか牛」や「くまもと黒毛和牛」などのブランド牛が有名ですが、そんな三大畜産物を抑えて県内で長年愛されているのが“馬肉”です。現在の食肉の主流となっている牛肉や豚肉などに比べると国内での生産量は約5,000トン前後とかなり少なく、生産地も限られていますが、その中でも特に生産量が多いのが熊本県で全体の約40%を占めています。県内では体格が大きく体重も重い重種馬(じゅうしゅば)を中心に生産しており、上質な霜降り(サシ)が多く入っているため口に入れた時のとろけるような食感と甘み、濃厚な旨みを感じられるのが熊本県の馬肉の特徴となっています。生産している馬の種類は産地によって異なり、見た目や特徴も異なることが多く、熊本県に次いで生産量の多い福島県では軽種馬(けいしゅば)と呼ばれる競走馬ほどの大きさの馬を中心に生産しているため、柔らかくもっちりとした食感とあっさりした味わいが特徴です。そのため、生産地や馬の種類によってまったく違った特徴を楽しむことが出来るのも馬肉の魅力となっています。
熊本県で馬肉を食べるようになったのは今から約400年前の安土桃山時代の頃、熊本藩の初代藩主・加藤清正が朝鮮へ出兵の際に食糧難に陥り、軍馬を食べてその場を凌いだことがきっかけとされています。しかたなく食べた馬肉でしたがそれが非常に美味しく、馬肉を気に入った清正は帰国した後も好んで食べるようになったため、県内で馬肉を食べる文化が少しずつ根付いていきました。もともと日本において馬肉を食べる食文化は古く縄文時代から続いていますが、江戸時代までは肉食が禁止されていたこともあり、馬肉を食べる習慣も少なかったです。しかし、栄養価の高さから薬膳料理として扱われるようになったことで庶民の間でも少しずつ食べられるようになり、明治に入って肉食の解禁や軍馬・農耕馬などとして馬を飼育するようになったことが影響して県内では馬肉を食べる人が増えていったとされています。一般的に食べられるようになったのは昭和に入ってからであり、戦後の食料難の際に馬肉を食べたことを機に県外でも馬肉の需要が増えていきました。以前までは一般的に食べられていた馬肉ですが、軍馬などとして馬を使う需要が減り、食肉も海外から入ってきた牛肉や豚肉が主流になると馬肉の生産量は年々減って、現在は限られた地域だけでしか生産されなくなってしまったのです。また、馬肉のことを別名で「桜肉」と呼ぶことがありますが、これは肉の色が桜のようなピンク色であったことに加えて、肉食禁止の時代の隠語として馬肉のことを「さくら」と呼んでいた歴史からその名残として呼ばれています。
馬肉は脂肪分が少なくヘルシーでタンパク質や鉄分・亜鉛・ビタミン・アミノ酸などの栄養素も豊富に含まれているため年々人気が高まっており、定番の馬刺しやユッケ、焼き物、鍋料理などさまざまな馬肉料理が食べられています。さらに、柔らかくて豚肉よりもクセが少ないため食べやすく、ロースやヒレ、モモ肉の他にもヒモ(あばら骨の肉)やネック(首)、コウネ(たてがみ)など他の肉ではあまり聞かない部位も多いです。特に生で食べる文化は日本独自のものとされており、これは馬の体温がもともと高く食中毒の原因となる細菌が繁殖しにくいことに加えて、徹底的な衛生管理や対策を行っている日本だからこそ生で食べることが出来ます。しかし、需要の高さに対して供給が追い付かないのが事実で、国産馬肉の味や質に近いカナダ産を中心にフランスやメキシコなどの海外から輸入することも多いです。また、県外や海外で生まれた馬を熊本で4か月以上肥育した馬肉には「○○産熊本肥育」や「熊本馬刺し」と表記し、生まれも育ちも熊本の場合は「熊本県産馬刺し」など、それぞれに違う表記をしています。熊本県で生まれ育った馬肉は非常に希少で出回ることが少ないこともあり、現在は基本的に前者の出生地の違う馬肉や海外産の馬肉が多いとされていますが、質の高さや味わいに遜色はないため、熊本県で美味しい馬肉を食べる際には食べ方や部位、馬の種類の他に産地などにも注目してみると馬肉の新しい魅力や美味しさに気づくかもしれません。
からし蓮根
シャキッとしたレンコンの食感と鼻に抜ける辛子の風味が特徴の“からし蓮根”は、熊本を代表する郷土料理の1つであり、定番のお土産としての人気も高いです。レンコンの穴に辛子と麦味噌を混ぜた特製の辛子味噌を詰め、卵黄と小麦粉、そしてウコン(ターメリック)を混ぜた衣をつけて油で揚げています。表面の衣と切った断面から見える辛子味噌の鮮やかな黄色が非常に印象的で、酒のつまみやごはんのおかず、さらに地元では正月のおせちにも欠かせない料理として親しまれていますが、現在は家庭で作る料理というよりもスーパーや専門店で購入したり、居酒屋などの飲食店で注文することの方が多いです。ほとんどのからし蓮根はレンコンを一節ずつ調理しているため、好みに合わせて食べやすい厚みにカットしてから食べるのが一般的で、辛子味噌のツンとした香りや味わいは日本酒や焼酎といったお酒との相性も抜群に良いです。また、醤油との相性も良く、からし蓮根の持つ旨みを引き立たせてくれるうえに、辛みも抑えてくれるため特におすすめの食べ方となりますが、なかには商品や好みによって辛みが強いと感じることもあるため、苦手な場合はマヨネーズやごまドレッシングなどをつけるとマイルドになり食べやすくなります。反対に辛いものが好きという場合は、電子レンジで15秒前後加熱してみて下さい。温まることで辛みが増し、揚げたてに近い風味を楽しむことが出来ます。
熊本県は古くから沼地が多く、たくさんの蓮が生い茂っていたことからレンコンの生産が盛んであり、その生産量は全国で上位に入るほどでもあります。そのため、レンコンを使ったからし蓮根が郷土料理であるということも納得の理由ですが、一体いつ頃から食べられている料理なのでしょうか?からし蓮根が誕生したのは今から400年ほど前の江戸時代と言われており、体が病弱だった熊本藩初代藩主・細川忠利の為に作られたのがはじまりとされています。忠利公は病弱であるが故に食が細く、栄養価が高く増血効能のあるレンコンを食べるよう勧められましたが「泥の中で育った不浄なもの」として手をつけることはなく、どうにか興味を持ってもらうために辛子味噌を詰め、珍しい料理としてからし蓮根が作り出されたのです。忠利公はからし蓮根を大変気に入り常食するようになったため、次第に体も丈夫に健康になっていったという歴史があります。また、輪切りにしたレンコンの形が細川家の家紋である九曜紋(くようもん)に似ていたことから、製造方法も含め門外不出の料理としていた過去があり、明治時代に入ってようやく庶民に広まったため、熊本県の名産品としてからし蓮根が古くから親しまれているのです。ちなみに、誕生当初は麦粉・空豆粉・卵を使った衣を使って揚げていたため、現在のような黄色い見た目ではなかったとされています。衣にウコンを加えて黄色い衣をつけるようになったのは明治以降ではないかと言われていますが、はっきりとした時期などは不明となっています。
からし蓮根の風味や食感を最大限に楽しむのであればそのまま食べるのが1番ですが、アレンジが出来るのも強みであり、適度な厚みにカットすれば天ぷらやソテーに、厚みや大きさを変えればサラダや炒め物などの具材としても使うことが出来ます。また、パンと辛子マヨネーズの相性が良いことからサンドイッチやハンバーガーの具材として挟むのもおすすめで、熊本市内にあるからし蓮根専門店ではコロッケに刻んだからし蓮根を加えたご当地バーガーを販売しており、観光客などからの評価も高いです。そのため、初めてからし蓮根を食べる人はアレンジ料理から入るのもよいでしょう。風味のついたレンコンチップスやスナック菓子なども販売されているため、幅広くからし蓮根の魅力と奥深さを味わってみて下さい。
太平燕
熊本県の中部を中心に食べられている“太平燕(タイピーエン/タイピンエン)”という郷土料理を知っていますか?白菜やにんじん、タケノコといった野菜とイカ、エビ、豚肉、きくらげなど五目と呼ばれる具材をたくさん使ったスープは一見、長崎ちゃんぽんにも似ていますが、使われている麺が中華麺ではなく春雨を使うのが太平燕の大きな特徴でもあります。県内の中華料理店では定番メニューとして取り扱いのある店舗が多く、ヘルシーな麺料理であるため特に女性からの人気が高いですが、食事や飲んだ後のシメ、さらには家庭や学校給食でも食べられているほど身近な料理であるため、老若男女問わず熊本県ではソウルフードとして広く親しまれています。スープは全体的にあっさりとしているものの、お店や作る人によって味が異なり、鶏ガラや豚骨ベースの醤油・塩などスープのベースがその店の特徴となっていることも多いです。さらに、ラーメンでは煮卵がトッピングとして使われることが多く馴染み深いですが、太平燕では揚げたゆで卵がトッピングされており、珍しさも含めて太平燕ならではの特徴となっています。
太平燕はもともと中国福建省の郷土料理であり、明治時代に海外に移住した華僑(かきょう)が熊本に渡った際に伝えられたと言われています。中国での太平燕は麺料理ではなく、アヒルの卵を入れたスープワンタンのような料理であり、ワンタンに使われる皮は豚肉を叩き潰してサツマイモのデンプンを練り込んだ「扁肉燕(ビェンニュッイェン)」という皮を使っているため特有の食感を持っています。別名では肉燕(にくえん)や燕(えん)とも呼ばれていますが、日本ではアヒルの卵や扁肉燕を簡単に入手することが出来ないため、アヒルの卵の代わりに揚げたゆで卵、扁肉燕の代わりに春雨を使うなど、日本でも作りやすく食べやすいようにアレンジしたものが独自の太平燕として熊本県に根付いているのです。ただし、普通のゆで卵やうずらの卵を使う場合や主に使われているコシの強い緑豆春雨ではなく、主原料が馬鈴薯でんぷんである日本産の春雨を使うなど、店舗によって使う卵や春雨の種類が異なることもあるため、スープ同様、具材の違いもお店の特徴として捉えられることが多いです。この他に、中国の高級食材である燕の巣の代わりに揚げたゆで卵、フカヒレの代わりに春雨を使ったスープが太平燕の原形となっている説もありますが、伝承した華僑は横の繋がりが強いこともあり、実際にはどこから伝わり、どの説が有力であるのかはっきりしていない点もあるとされています。
県内では熊本城の周辺を中心に太平燕が食べられるお店が集まっており、具材やスープの違いによってあっさりしているものから旨みの強いもの、コクを感じられるものといった味わいを楽しむことが出来ます。特に使われている春雨は同じように見えて特徴が違うものが多く、コシが強い、もちもちしている、太めで食べ応えがある、細くてのどごしが良い、スープが絡みやすいなど春雨によって太平燕そのものの印象を大きく変えることも多いため、ぜひ食べ比べをしてお気に入りの太平燕を見つけてもらいたいです。
熊本ラーメン
日本各地で食べられているご当地ラーメンは、その土地の風土や歴史によって味やトッピングなどの特徴も大きく変わり、醤油・塩といった定番の味から個性的な種類までさまざまなラーメンが食べられています。特に福岡県をはじめとする九州では全体的に豚骨ラーメンが多い傾向にあり、博多ラーメンを中心に久留米ラーメンや鹿児島ラーメンなどスープの濃厚さやトッピング、麺の太さなどジャンルの違う豚骨ラーメンが根付いています。なかでもクセが少なく香ばしい風味を楽しめるのが熊本県のご当地ラーメン“熊本ラーメン”です。熊本ラーメンは豚骨をベースにしながらも鶏ガラを加えて作っているお店が多いため、マイルドでコクを感じられるスープが特徴になります。また、豚骨ラーメンでは細麺を使うことが多いなか、中太ストレート麺を使っていることも熊本ラーメンならではとなっており、しっかりとした歯ごたえとボリュームから食べ応えもばっちりです。これは熊本県では基本的に替え玉をする文化がないため、博多ラーメンなどに比べると提供時の麺の量が多めであることも影響しており、さらに量を食べたい人は最初に大盛りで注文するのが一般的な注文方法となっています。そして熊本ラーメンの特徴として忘れてはいけないのが、マー油とニンニクチップです。具材にはチャーシューやきくらげ、メンマなど豚骨ラーメンではよく見かける種類をトッピングしていますが、これに加えて揚げて焦がしたニンニクチップやマー油というニンニクを揚げた時の油を追加することで、他の豚骨ラーメンでは味わえない香ばしさとクリーミーな味わいを生み出し、熊本ラーメンの大きな特徴として親しまれているのです。
今でこそ豚骨ラーメンの代表格と言えば博多ラーメンの印象が強いですが、発祥は久留米市であり久留米ラーメンの方が歴史は古く、九州の豚骨ラーメンは久留米の影響を受けて誕生したものが多いとされています。熊本ラーメンもその1つであり、戦後に開業した三久(サンキュー)という屋台ラーメンがルーツとされています。この三久は豚骨ラーメンの特徴である白濁したスープを作ったお店としても有名で、その美味しさを伝えるために鹿児島県以外の九州各県に白濁した豚骨ラーメンを広めます。熊本県では玉名市に屋台を構えると口コミで一気に人気になり、このラーメンを食べに出かけた3人の青年によって熊本ラーメンは作り出されたのです。この青年たちはもともと、不動産業や中古車販売業などラーメンとは関係のない仕事を営んでいましたが、大水害の被害によって事業が上手く進まなくなり、感銘を受けた久留米ラーメンを新しい商売として始めました。当時、熊本市内にラーメン店はほとんどなく、ちゃんぽんが多かったことや自分たちの作るラーメンに物足りなさを感じていたことなどから試行錯誤をした結果、熊本ラーメンの特徴でもあるニンニクチップをトッピングするようになりました。また、ニンニクを使うようになったのは、隣接する玉名市が海苔の養殖が盛んで労働者の身体を温める目的や活力をつけてもらうためでもあったそうです。その後、各自独立してお店をオープンさせ、県外に出店するなど少しずつ熊本ラーメンの認知度を広めていきました。そのため、現在は数あるラーメン店の中でも熊本ラーメン発祥の店として認知され広く親しまれているのです。県内にはマイルドな味わいながらも、あっさりから濃厚、さらには超濃厚まで幅広い熊本ラーメンが熊本市を中心に各地で作られており、具だくさんなものや真っ黒な見た目なもの、ニンニクがたっぷり使われているものなど各店舗でそれぞれの特徴を感じられるラーメンを食べることが出来ます。非常に奥の深い九州の豚骨ラーメンの中でも個性溢れる特徴を持つ熊本ラーメンだからこそ、その美味しさも実感しやすいでしょう。ぜひ、熊本県を訪れる際には熊本ラーメンを食べて豚骨スープの違いとニンニクとの相性の良さを堪能してみて下さい。
いきなり団子
熊本県には“いきなり団子”という郷土菓子があります。和菓子だという予想は出来るものの、そのユニークな名前からは一体どのようなお菓子か予想がつかないのではないでしょうか。いきなり団子とは、1cmほどの厚さに輪切りにしたサツマイモと小豆あんを餅や小麦粉を練って作った生地で包み、蒸したお菓子になります。団子という名前からみたらし団子のような串に刺さった和菓子を想像する人もいるかと思いますが、実際には串には刺さっておらず、どちらかと言えば大福のような見た目で手のひらに収まるサイズのものが一般的です。サツマイモのホクホクとした食感と優しい甘さ、もちもちの生地、そしてお店によって甘さ控えめや塩味を感じるなど全体のバランスを考えて調整された小豆あんとの組み合わせが美味しさの秘訣となっています。サツマイモと小豆あんのスタンダードな組み合わせは生地が白いものが多いですが、他にもよもぎや栗、紫芋、桜、黒糖などあんの味が違う商品も多く、味に合わせて包んでいる生地の色が変わるのも特徴です。
いきなり団子が生まれた詳しい時期ははっきりとは分かっておらず、江戸時代から続くほど古いという説もあります。阿蘇山のある熊本県では火山灰の影響もあり、サツマイモを栽培するのが盛んな地域が多く、昔からサツマイモが身近にある環境でした。そのため、かつては輪切りにしたサツマイモを生地で包んで蒸しただけのシンプルなおやつであり、サツマイモの収穫をする際に作業の間のおやつとして食べられていました。特に菊池平野や熊本平野の農家ではよくいきなり団子が作られていたそうで、短時間で簡単に作ることが出来ることから熊本弁で簡単や手早いを意味する「いきなり」という言葉が名前として使われるようになりました。また、急に祖母の家に遊びに来た孫たちのために家にある材料で団子を作ったという話が名前の由来とも言われているため、急な来客があった際にもいきなり団子が重宝されています。非常にシンプルなお菓子ですが時代背景によって少しずつ変化しており、米が貴重な時代には小麦粉のみで生地が作られていたことや砂糖が手軽に手に入るようになってからは甘みを調整した小豆あんを入れるようになったなど、いくつかの改良があって現在の姿が浸透し定着しています。
近年はサツマイモの品種が増えていることもあり、甘さや食感などサツマイモの特徴に注目して使っているお店も多く、つぶあんかこしあんか、小豆あん以外の種類かなどと合わせるとより違った印象を受けやすくなっています。数十年前に小豆あんが入るようになってから、いきなり団子は進化する一方で、本来は蒸したての温かい状態で食べますが、冷やしたものや凍らせたいきなり団子を半解凍してシャーベット状を楽しむもの、蒸すのではなく焼く・揚げる、さらにはカレー味や阿蘇辛子高菜味、りんごのコンポートを入れたものやパイ生地を使った洋風のものなど、あんの味違いに加えて進化系のいきなり団子も増えており、バリエーションが豊富です。自宅でも簡単に作ることが出来ますが、熊本市を中心に県内では特徴の違うオリジナルのいきなり団子を販売している専門店や和菓子店が多いため、食べ歩きのお供やお土産にいきなり団子を購入してみてはいかがでしょうか。