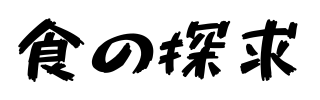島根県は多くの神話が伝わることで有名な県であることから、日本最古の神社の1である出雲大社には毎年多くの参拝客が訪れます。そのため、出雲大社周辺で食べられるグルメや出雲発祥の名産品の人気が非常に高いですが、県内にはまだまだ魅力がたっぷり詰まったグルメや特産物がたくさんあります。今回はそんな知っているようで知らない人も多い島根県の特産物や名産品について紹介していきたいと思います。
出雲そば
島根県といえば“出雲そば”といっていいほどその人気や認知度も高く、県を代表するグルメや郷土料理としてもよく知られています。出雲大社を訪れた際に食べたいとされる料理の1つであり、日本三大そばの1つでもある出雲そばですが、食べたことがない人からすると普通のそばと何が違うのか分からないという人も多いのではないでしょうか。出雲そばには特徴がいくつかありますが、特に印象強いものが提供の仕方やその見た目です。出雲そばは大きく分けると冷たい「割子そば」と温かい「釜揚げそば」の2種類に分けられますが、特に割子そばの方が食べられる割合が多く、出雲そば=割子そばという印象を持っていることも多くあります。「割子(わりご)」とは漆塗りをした丸い朱色の器のことであり、この割子にそばが盛りつけられて提供されます。しかし、ざるそばなどとは違い三段で一人前として提供されるのが一般的で、食べ方も器を三段重ねた状態で一段目に直接つゆと薬味をかけ、食べ終えた後、残ったつゆを二段目に移します。さらにつゆや薬味を足して二段目も食べ終えた後は三段目も同じ食べ方をし、最後にそば湯を入れて飲むというのが流れとなっています。食べ終えた器は一番下に重ねて、常に三段の状態で食べるというのが正しい食べ方とされているため、全国的に見ても珍しい食べ方をするそばでもあるのです。
島根県では平安時代からそばの実を栽培していたため身近な食べ物でしたが、そばとして食べられるようになったのは江戸時代になります。江戸幕府の命令で行われた転封(大名の国替え)により信州松本城の城主・松平直正が島根県に移動する際、そば職人も同行させたことが島根県でもそばを食べるようになったきっかけとなりました。もともとそばの実の栽培が盛んだったこともあり、県内ではそばがあっという間に広まって普及し、次第に出雲大社に訪れる参拝客や武士などにも提供されるようになっていったと言われています。この時にお弁当の代わりとして作られたのが割子そばであり、当初は使い捨てが出来る白木で作った器や持ち運びを重視したタンス型などもありましたが、抗菌・殺菌効果を高めるために漆が塗られた器が採用され、洗いやすいというメリットから現在の丸い形へと変化していったそうです。また、もう1つの食べ方である釜揚げそばは、出雲大社の参拝客に提供するために神社周辺で始めた屋台版の出雲そばであり、特に全国の神様が集結する「神在祭」が行われる旧暦の10月にはより多くの参拝客に温かい新そばを振る舞っていたとされています。屋台ではそばを茹でた後に水で締める工程が出来ないことから、茹でたそばをゆで汁(そば湯)と一緒に器に盛りつけ、ネギや鰹節などの薬味だけがトッピングした状態で提供されます。そのため、食べる直前に濃いめのつゆを自分でかけて、好きな濃さに調整してから食べるのが釜揚げそばの特徴にもなっているのです。
出雲そばは玄そばという殻がついた状態のそばの実をそのまま挽いた「挽きぐるみ」という種類のそば粉が使われているため、やや黒っぽい見た目をしており、そばの実本来の香りや味わい、しっかりとした食感を感じられるのも特徴です。また、挽きぐるみを使った出雲そばは栄養素の高さも魅力の一つであり、豊富に含まれるビタミンやミネラル、ポリフェノールの1種であるルチンなどによって疲労回復など健康に良い効果を期待することが出来ます。割子そばと釜揚げそばは提供の仕方や温度、食べ方は異なりますが、どちらも使っているそばは挽きぐるみであること、食べる直前に自分でつゆをかけることが共通の特徴となっており、定番の薬味もわさびではなくもみじおろしが多いというのも出雲そばならではと言ってよいでしょう。出雲そばと呼ばれている割子そばと釜揚げそばは、どちらとも出雲大社が大きく影響して発展していった食べ物であり、古くから地元で根強く親しまれています。ぜひ、出雲に訪れた際には割子そばだけでなく、釜揚げそばも食べて特徴や食べ方の違いも楽しんでみて下さい。
宍道湖しじみ
旨みがたっぷり詰まったしじみのみそ汁は心も体も温まる料理として、子供から大人まで幅広い年齢層の人に愛されています。そんな“しじみ”は日本では古くから親しまれている貝の一種であり、市場に出回るヤマトシジミ、琵琶湖に生息するセタシジミ、淡水の水田や小川に生息するマシジミの3種類が日本には生息しています。特に島根県の松江市と出雲市にまたがる宍道湖(しんじこ)はしじみの産地としても有名であり、その漁獲量は日本一、全国の4割を宍道湖産のしじみが占めています。宍道湖に生息しているしじみは最もポピュラーなヤマトシジミになりますが、他県で漁獲されるヤマトシジミよりも大粒で質が高く、肉厚でもあるためしじみの中では特に美味しいと評判も高いです。そのため島根県のしじみは「宍道湖しじみ」という名称で認知されていることも多く、身が大きいからこそみそ汁やスープなどの汁ものだけでなく、アヒージョやホイル焼き、酒蒸しなどさまざまな料理に重宝されているのです。
淡水と海水が混ざりあう宍道湖は日本の中でも最大の汽水湖であり、しじみにとって良好な育成環境だったことが宍道湖しじみの大きさや質の高さに大きく影響しています。しじみの貝殻は泥地で育ったものは黒く、砂地で育ったものは黄色くなるなど、育った湖底環境によって色や形が変化しますが、その環境の幅が広い宍道湖では黒色や茶色がかった黒を中心に茶色や黄褐色、希少な黄色などのしじみが獲れることもあります。また、通常しじみは貝の幅によって規格を決めることが多いですが、宍道湖しじみは貝の厚みによって規格が決められており、Sサイズから2Lサイズまでの大きささが決められています。1年を通して漁獲されるしじみには年に2回旬の時期があり、産卵のために身が肥えてプリっとした食感の「土用シジミ」が獲れる7月前後と冬を越すために栄養をたっぷり蓄えた「寒しじみ」が獲れる1月~3月上旬までの期間に漁獲されたものは格別と言われているため、いつも以上に美味しい風味や食感を味わうことが出来るでしょう。
島根県では奈良時代からしじみ漁が行われてきたと言われており、伝統的な食文化といっても過言ではありません。特に出雲地方では郷土料理としても「しじみ汁」が親しまれ、日常的に食べられています。昭和30年まではしじみの価格が低かったことや漁師の数も少なかったことによりしじみ漁自体があまり盛んではありませんでしたが、昭和40年代に入ってしじみの数が全国的に減少したことがきっかけとなり、宍道湖でのしじみ漁が盛んになっていったのです。宍道湖は一般的な湖とは違う汽水湖であることが大きな特徴になりますが、それ故に水深4m以上ある場所では濃い塩水が軽い塩水の下に溜まり、水中の酸素濃度が著しく低下した水塊が出来てしまうことから酸素が足りず、しじみが生息することが出来ません。そのため、湖全体に生息しているのではなく、沿岸部を中心に水深0m~4mの辺りまでが漁場となっています。現在、宍道湖でしじみを漁獲する漁師は約300名いると言われており、人力で行う手搔き操業や機械を使った機械搔き操業、浅瀬で行う入り搔き操業など漁師や団体によってその方法はさまざまです。また、しじみは漁師1人につき約100Kg以内に収まるよう採捕量が制限されており、宍道湖のしじみを保護するための規定や制限を作るなどいくつもの取り組みが行われています。現地に行くことが一番新鮮でおいしいしじみを食べられる方法にはなりますが、島根県に行く機会が少ない方には手軽に購入出来るお取り寄せを使うのがおすすめです。他にも、貝がそのまま入ったみそ汁やスープ、エキスを粉末状にした調味料、オイル漬け、ラーメンなどの加工品にも力を入れており、普段使いからお土産まで広く使えるため人気があります。栄養も豊富で疲労回復や二日酔い防止などにも効果が期待出来るため、美味しい宍道湖しじみを食べて一般的なしじみとの違いを楽しみながら一緒に健康も取り入れてみてはいかがでしょうか。
あご野焼き/赤天
“あご野焼き”とは、トビウオのすり身を使って焼き上げた練り物であり、山陰地方を代表する特産品でもあります。あごが落ちるほど美味しいという理由などから「あご」と呼ばれるようになったトビウオの頭や内臓、皮、骨を丁寧に取り除いてすり身にし、金属製の心棒に筒状になるように練りつけて炭火で焼きあげます。そのため、ちくわのような見た目をしていますが、原寸サイズは直径が約7cm前後、長さは50~70cm、重さも約1.5kgとかなり大きく、噛み応えもあるため食べやすい大きさや厚さに切って食べるのが一般的です。生食で食べられるため、何もつけずにそのまま食べると素材本来の風味を最大限に味わえるためおすすめですが、軽く炙ってから醤油やわさび醤油をつけると一味違った風味も楽しめます。また、すり身にする工程では日本酒や焼酎といった地酒を加えているため、トビウオの旨みや甘み、表皮の香ばしさと一緒に地酒の香りが口に広がるのも特徴です。近年は地酒を使うことが多くなりましたが、以前は古くから出雲地方に伝わる「地伝酒」という清酒よりも甘みの強い調理酒を使うことが多く、現在もメーカーなどによって伝統の製法で作り続けられているあご野焼きには地伝酒が使われており、独特な旨みや芳醇な味わいも楽しむことが出来ます。
あご野焼きの歴史は古く、江戸時代には食べられていたと言われている伝統食です。島根県では水揚げされた魚介を使った加工品の生産が昔から盛んに行われており、山陰沖に泳いできたトビウオが5月~9月にかけて豊富に漁獲されることからあご野焼きが作られるようになりました。当時は今のように魚介を保存する技術がなく、新鮮なうちにすり身にして保存食として持ち帰ったのがはじまりとされており、かまぼこの原形ともいわれています。炭火で焼くため外で作業が行われていたことから「野焼き」という名称がつき、戦前までは初夏になると揃って野焼きが行われて香ばしい香りが辺り一面に漂っていたため、松江ならではの初夏の風物詩でもありました。現在は1年を通して作られていますが、旬の5月~9月、特に産卵後の6月~7月はトビウオに脂が乗っていることもあり、この辺りに作られたあご野焼きは特に絶品と評判も高いです。旨みや甘みが強いためごはんや酒のお供はもちろんのこと、子供のおやつや突然の来客時のお茶請けとしても食べられているほど、地元の人々から親しまれています。
県内ではあご野焼きの他にも県民を中心に愛され続けている練り物がもう1つあります。それが“赤天”です。近年は東京など他の地域でも見かけることが増えている赤天は浜田市の名物であり、魚のすり身を赤く色づけてパン粉をまぶして揚げているため、さつま揚げのようなモチモチとした食感と同時にパン粉のサクサクとした食感を楽しめるのが特徴です。また、赤唐辛子を練り込んでいるためピリッとした味わいを感じられるのも特徴で、一般的な練り物とは異なる風味や食感がクセになるとリピーターが続出するほど人気があります。そのままでも美味しく食べられますが、マヨネーズや生姜醤油との相性もよいことからビールなどのおつまみとしてよく食べられていますが、他にもおでんや煮物、チャーハン、サンドイッチなどのさまざまな料理の具材にも使える万能さも持ち合わせているのです。赤天の誕生についてはっきりとした歴史は分かっていませんが、戦後少し経った頃に浜田市内にあるかまぼこ店で作られたオリジナルのかまぼこであり、誕生してから長いこと地元の方に親しまれてきました。そのため、県内にあるスーパーや居酒屋では定番商品として取り扱われていることがほとんどになります。まったく違った歴史や特徴を持つあご野焼きと赤天ですが、どちらも県内で愛され続けてきたからこそ、お土産としても人気が高く、その美味しさは今や全国まで届く勢いとなっています。あまり見かけない種類の練り物でもあるため、ぜひ島根県を訪れた際にはあご野焼きと赤天もチェックしてみて下さい。
十六島のり
おにぎりには欠かせない海苔は海藻と呼ばれる海に生息する藻類から作られていますが、その海藻にも種類があるため原料に何が使われているか、また加工方法によって海苔の種類も分かれます。特に日本海側の岩場に多く自生する天然海苔(アマノリなど)は「岩のり」と総称されており、養殖のものと比べるとやや硬めの食感と磯の香りを強く感じられるのが特徴です。その中でも島根県では“十六島のり(うっぷるいのり)”という高級の岩のりが採れることで知られており、島根半島の西部、出雲市十六島町の海岸において12月~2月の短い期間の中でしか収穫することが出来ません。さらに生産者は20軒以下、年間の生産量も1トン未満と希少であるため、そのほとんどが県内で消費されてしまい、県外に出荷されることは限りなく少ないです。しかし、冬場の荒波という厳しい環境の中で育った十六島のりは、シャキシャキとした歯ごたえと磯の風味をしっかり感じられるのが大きな特徴となっており、古くから名産品として扱われています。
奈良時代に書かれた出雲国風土記にも記述されているほど古くから十六島では質の良い海苔が採れる場所であったため、奈良時代や平安時代には朝廷への献上品としても使われていた高級品でした。さらに、江戸時代には松江藩主から幕府の要人に贈答品として贈られていたともいわれています。冬場の限られた期間に収穫される十六島のりは「シマゴ」と呼ばれる人たちによって手作業で収穫されていますが、岩場という足場の悪い立地だけでなく、高波や強風、足元のぬめりなどにも注意を払わなければならないという過酷な環境下で作業が行われています。この地方では別名で「かもじのり」とも言われており、艶のある黒い色が女性の美しい黒髪のような色を連想させたことからその名が使われているそうです。収穫後に乾燥させた十六島のりは汁物や茶碗蒸しなどの具材、天ぷら、そばやお茶漬けの薬味などとして食べられることが多く、風味を豊かにしたい時などに重宝されています。また、昔から邪気や厄を払う食べ物としても親しまれてきたことから正月には雑煮に入れるのが習わしとなっており、その年の邪気を払い難病を逃れる縁起物としても食べられてきました。海苔の加工品の定番である佃煮も人気があり、ごはんやお酒のお供としても食べられていますが、近年はパスタやピザといった和食以外の料理にも使われるなどジャンルに縛られることなく使用されることが増えています。海藻である海苔にはカリウムや亜鉛、鉄分をはじめとするミネラルや食物繊維が豊富に含まれており、肌荒れ・むくみ・貧血の予防や腸内環境の改善など、特に女性にとって嬉しい働きを期待することが出来るでしょう。近年は温暖化の影響でさらに希少価値が進んでしまっていますが、ネットを通して購入出来るお店も増えているため、普段食べ慣れている海苔では味わえない十六島のりの風味や食感を直接味わって楽しんでみて下さい。ギフトなどにもおすすめです。
和菓子/出雲ぜんざい
島根県は京都や金沢と並んで「日本三大菓子処」として有名ですが、これは江戸時代、松平治郷(まつだいらはるさと)が松江藩の7代藩主であったと同時に「不昧(ふまい)」と呼ばれる江戸時代後期を代表する茶人の1人であったことが大きく影響しています。不昧公の活躍によって松江の和菓子は大きく発展し、行事や稽古事としてではなく、住人たちが自然とお茶を嗜むといった身近なものであることが松江の和菓子の特徴でもあるのです。見た目はシンプルですが色鮮やかな種類が多く、明るい若草色が特徴の求肥を使った「若草」、紅白色で対となる落雁の「山川」、ホロっとした食感と鮮やかな黄色が美しい「菜種の里」、和三盆で仕上げた繊細な「姫小路」、餅菓子に皮ごとすりおろした柚子を練り込んだ「つぶつぶ柚餅子」、表面のカリっとした食感が楽しい「薄小倉」などが代表的な和菓子になります。どれも松江の四季の移ろいなどを形状や色合い、口当たり、食感などで表現しており、数多くの賞を受賞するなどその評価も高いです。特に若草・山川・菜種の里は不昧公が好んでいた和菓子であったため「松江の三大銘菓」としても認知されており、市内にある多くの和菓子店では定番商品として販売されています。天災などにより財政難に苦しんでいた松江藩を立て直した松平治郷は茶の湯にも熱心であり「不昧流」という作法やしきたりより「もてなしの心」を大切にする茶道を大成させ広めていきました。こうした背景などが京都や金沢よりも和菓子がより身近な存在にある理由なのかもしれません。そのためか、若草をはじめとする代表的な松江の和菓子は明治時代以降に一度姿を消してしまっていますが、市民や和菓子職人の熱意によって復活し、現在も銘菓として愛され続けているのです。
県内では松江だけでなく出雲地方でも古くから地元の人に愛され続けている和菓子があります。出雲の伝統和菓子である“出雲ぜんざい”は、味が豊かな出雲大納言という大粒の小豆を使っており、一般的なぜんざいよりも汁気が多く赤と白のお餅が一つずつ入っているのが特徴です。紅白の華やかな見た目は縁起がよく、出雲大納言の優しい甘さと合わさって人気の秘訣となっています。出雲では毎年旧暦の10月に全国から八百万の神様が集まる「神在祭」が行われ、この神在祭に集まった神様たちへのもてなしとして用意された神在餅(じんざいもち)が出雲ぜんざい誕生のきっかけになります。江戸時代の文献には「赤豆を煮て汁を多くし、少し餅を入れたもの」が神在餅として記述されており、このじんざいが出雲弁で訛って「ずんざい」、さらに変化して「ぜんざい」になったと言われているため、全国で食べられているぜんざいの発祥は出雲でもあるのです。特に出雲大社周辺の観光スポットなどでは出雲大社の御祭神である大黒様やハートのモナカが添えられたぜんざい、お餅ではなく紅白の白玉団子を使ったぜんざい、抹茶を使ったぜんざいなど、お店によるこだわりが見られる出雲ぜんざいを食べることが出来ます。出雲大社の周辺で食べられるため、気軽に立ち寄りやすいのもポイントが高いですが、松江では抹茶や和菓子が楽しめる茶室やカフェ、和菓子作りが体験出来る施設などが多く、さらに毎年4月24日と毎月24日は茶の湯の日として気軽にお茶や和菓子を楽しむといった記念日が作られています。秋には松江城で大茶会が行われるなどお茶まつわるイベントも多くあるため、より和菓子やお茶が好きという人には松江の方が幅広く楽しむことが出来るでしょう。どちらも古くから親しまれてきたからこそ、その土地で生まれた和菓子が根付いているため、和菓子を食べて歴史を感じながらいつもとは違った素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。