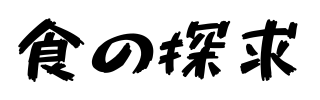坂本龍馬や板垣退助をはじめとする歴史上の偉人を多く輩出してきた高知県は、温暖で海と山に囲まれた自然豊かな県です。さらに四万十川や仁淀川といった水質の良い綺麗な川も流れているため、野菜や果物、地鶏・和牛などの畜産物、太平洋を泳ぐ海産物、さらにはアユやうなぎなどの川魚まで高知県の中だけでも多様の美味しい特産物がたくさん生産・漁獲されています。食材の宝庫とも呼ばれ、県民の9割が食べ物が美味しいと感じている高知県の特産物について今回は紹介していきたいと思います。
鰹
スズキ目サバ科の回遊魚である“鰹”は高知県の代表的な魚であり、県内では日常的に食べられている食材でもあります。かつおのたたきをはじめとする鰹料理はソウルフードとしても親しまれているため、漁獲量も多いかと思いきや実際にはそこまで多いわけではなく、静岡や宮城、東京、三重といった他県の方が多く漁獲されているのです。しかし、消費量は全国で1位を誇るほど高く、特に高知市は年間の支出金額が1世帯当たり約8,000円と2位に位置づけする市と2倍以上の差をつけるほど群を抜いて高い傾向にあります。回遊魚であるため常に泳いでいる鰹は血液や脂肪が多く、旨みが強い反面、鮮度が落ちやすく、血生臭さを感じやすいことから好き嫌いが分かれやすい魚となっています。しかし、県内には鮮度の高い鰹が多く出回っており、漁師だけでなく県民も鰹の味にこだわりを持っていることから、他県で食べる鰹とは比べものにならないくらい美味しく、もちもちとした食感と生臭さを感じにくいのが大きな特徴です。また、鰹には旬の時期が年に2回あり、3月~5月に旬を迎える初鰹と9月~11月が旬の戻り鰹によっても特徴が違います。初鰹は通常よりも小ぶりで身が引き締まっていることから、脂が少なくさっぱりとしており、特有のにおいも少ないため苦手な人も食べやすいと言われています。反対に一度北上した鰹が温かい水域に南下する戻り鰹は比較的大きく、脂も乗っているため、もちっと柔らかくとろけるような食感が楽しめます。また、旬以外にも、初鰹と戻り鰹の中間くらいで脂と身のバランスがよい夏鰹やシーズンオフの冬場に見られる希少性の高い迷いガツオなど季節問わずに特徴の異なる美味しい鰹が食べられるのが高知県の強みでもあります。
ここで気になるのは、漁獲量はそれほど多くないにも関わらずなぜ消費量が多いのかということですが、これは高知県の立地が関係しており、漁場が近いため漁獲されたばかりの新鮮な鰹を持ち帰りやすいことが大きく影響しています。さらに黒潮も近く、旬の鰹が高知県の近海まで近づくため、美味しい鰹が出回りやすくなっているのです。漁獲方法にも特徴があり、全国で多く用いられている漁法は円形に展開した網を使って効率よく鰹を漁獲する「巻き網」を用いることが多いなか、高知県では「一本釣り」という漁法を取り入れており、鰹の群れにイワシなどの小魚を投げ込んでおびき寄せ、釣り針を使って一匹ずつ釣り上げる方法になります。巻き網に比べると効率こそ下がりますが、一匹ずつ釣るため鰹が傷つかず傷みにくくなることに加えて、鮮度の高いうちに冷蔵や冷凍保存することも出来るため、品質の高い状態で鰹を持ち帰ることが可能になります。また、生食に向いていない鰹を排除し加工用に回していることや古くから鰹を食べているからこその目利きの良さ、美味しく食べるための知恵と工夫が備わっていることも高知県の鰹が美味しい理由に繋がっているでしょう。
県内で食べられている鰹料理の中でも特に人気が高いのが郷土料理でもある「かつおのたたき」です。藁を使って皮目を焼き、玉ねぎやミョウガなどの薬味を乗せて食べるたたきは、藁の香りが鰹の旨みを引き立たせてくれるのが特徴になります。たたきの誕生には、食中毒により生食を禁止された江戸時代において生まれた知恵や漁師がまかないとして食べていたものが広まったなど諸説あるとされていますが、たたきにすることで生臭さや磯臭さを抑えることが出来るため全国でもポピュラーな食べ方として親しまれています。通常は醤油やポン酢、特製のタレなどを使って食べますが、県内では塩で食べる「かつおの塩タタキ」の人気も高く、鮮度が高く生臭さを感じにくいからこそ鰹本来の美味しさを感じやすくなっています。他にも、刺身やカルパッチョ、なめろう、酒盗など県内では新鮮な鰹を使った料理やオイル漬け・フレーク・ジャーキーなど他県では見かけない加工品も多く販売しているため、高知県に訪れた際には思う存分、美味しい鰹を堪能してみて下さい。
生姜
ピリッと辛く特有の爽やかな香りを持っている“生姜”は、生姜焼きなど料理の味付けから肉・魚の臭み消し、さらにはスイーツにも使える香辛野菜です。高知県は生姜の生産量が全国で1番多く、国内で生産されている生姜の半分弱が高知県産になります。現在、日本で最も生産されているのは「土佐一」という塊茎が大きく分茎力の高い品種であり、すりおろした時の香りは強いですが辛みがマイルドで、繊維も少なく舌ざわりが滑らかなのが特徴であるため、さまざまな料理にも使いやすく、名物の鰹のたたきにも欠かせません。高知県でも土佐一が主要品種となっていますが、さらに県内では日本独自の品種である「金時生姜」の栽培も行っており、一般的な生姜よりも色が赤く、香りと共に辛みも非常に強いのが特徴です。高知県産の生姜はどちらも品質が高く栄養も豊富であり、特有のジンゲロールやショウガオールといった成分も含まれていることから、血行や腸内環境の改善、殺菌作用、冷え性や風邪の予防、新陳代謝・エネルギー消費量の促進など健康を維持するために必要な効果を期待することも出来ます。
生姜はもともと熱帯アジアが原産国で、日本には2~3世紀頃に中国から伝わり徐々に国内でも栽培するようになったと言われています。高温多湿を好み寒さに弱い性質を持つ生姜は、雨量が多く日照時間の長い高知県の環境が栽培するのに適しており、大正初期に大生姜の苗を取り入れたことをきっかけに、県内でも生姜を栽培するようになりました。また、昼夜の寒暖差が激しいことや四万十川から得られる豊富な水源、川を囲む山々の土壌といった条件も整っていたことが生産を拡大させる理由になったのと同時に、生姜のピリッとした辛みと爽やかな香りは暑い季節の食事に重宝されるなど、多くの高知県民を魅了したことも生産が広がっていった理由に繋がっています。現在は高知市や土佐市、四万十町を中心に県内のいたるところで生姜が栽培されており、自然環境を生かした露地栽培とハウス栽培の両方が取り入れられていますが、高知県の豊かな自然の中で育った露地栽培の生姜は実が締まり、ハウス栽培や他県で栽培したものでは味わえない食感や風味を感じられると評価も高いです。生姜は大きさや出荷時の状態によっても呼び方が変わりますが、私たちがスーパーなどでよく購入する黄色みのある生姜は「囲い生姜」と呼ばれ、10月~11月に収穫された後、定温・定湿の貯蔵庫で保存され1年を通して出荷されています。囲い生姜に対して少し早い初夏に収穫されるのが「新生姜」です。白い見た目をしている新生姜は通常の生姜よりもみずみずしくて柔らかく、シャキシャキとした食感とほのかな甘みを感じられるため、生の状態でも食べることが出来ます。ガリなどの酢漬けにされることも多く、期間が限られていることや囲い生姜とは異なる食感や風味が楽しめ、主役として料理にも使えることから人気も高いです。ちなみに、この新生姜を寝かせて水分が抜け、色も変化していったものが囲い生姜として出荷されています。
古くから生姜が身近にあり愛され続けている高知県では生姜を使った加工品にも力を入れており、定番のごはんのお供やシロップ、パウダーをはじめスープや佃煮、カレーなど多くの加工商品が販売されています。さらに、昔から茶菓子などでも食べられている生姜糖や有機生姜をたっぷり使ったジンジャエールなど、こだわりの詰まった商品も生産されており、美味しさと使い勝手の良さから日常使い以外にも、ちょっとした贈り物やお土産としての人気も高いです。生姜の種類や生か加工品かによっても風味は大きく異なりますが、普段の生活に高知県で作られた風味豊かな生姜を取り入れて、料理にも健康にもアクセントをつけてみてはいかがでしょうか。
文旦
みかんやゆず、オレンジなど日本では数多くの柑橘類が生産されていますが、高知県では“文旦”という柑橘類が栽培されているのをご存じですか?文旦は上品な甘酸っぱさとほのかな苦みのバランスが良く、プチプチとした食感の果肉を味わえるのが大きな特徴で、みかんなどに比べると認知度は低いものの人気は高く、取り寄せなどのリピート率も高いです。県内では「土佐文旦」と「水晶文旦」が作られており、それぞれの特徴も大きく異なっています。生産量の多い土佐文旦は黄色く分厚い皮とプリっとした果肉が特徴ですが、露地栽培かハウス栽培かによっても特徴や旬の時期が異なり、露地栽培は1月中旬~3月下旬、甘みと酸味のバランスが良く、日が経つにつれて少しずつ甘みの方が強く感じられるように変化していきます。ハウス栽培で作られる土佐文旦は露地栽培よりも旬が早く、11月下旬~1月中旬、はじめから甘みも強く蜂蜜のようなコクも感じられるのが特徴です。寒さに弱い性質からハウス栽培のみで作られる「水晶文旦」は9月下旬~11月上旬に旬を迎え、この中では1番糖度が高いのが大きな特徴になります。青りんごのような薄緑の皮は薄くて柔らかく、甘さと共に香りも高いため、生のまま食べるとよりその美味しさを実感しやすいでしょう。また、果肉は宝石に例えられるような透明度と輝きを持ち、非常にジューシーでもありますが、生産量が少なく希少であることから、ふるさと納税の返礼品や贈答品としての需要も高いです。
マレー半島が原産の文旦は室町時代の末期に九州に伝わったため、九州と四国を中心に地方品種の文旦類が栽培されており、現在は呼び方や特徴の違う15品種が日本で作られています。しかし、その生産量は高知県が圧倒的に多く全体の95%を占めているため、文旦といえば高知県というイメージが強いのです。ちなみに、愛媛や長崎で栽培されている大型の柑橘類である「晩白柚(ばんぺいゆ)」も文旦類の一種で、別名でザボンとも呼ばれ親しまれています。高知県で文旦の栽培を始めたのは昭和初期の頃、日本で最も多く栽培されている土佐文旦の木を鹿児島県から持ち帰ったことからはじまりました。一樹しかなかった原木をもとに増殖させた苗を土佐市の農家に植え少しずつ増やしていったそうです。当初、日本原産ではない文旦の栽培方法が分からず、試行錯誤しながら育てたため、栽培者は大変苦労したそうですが、日本で見たことのない文旦を販売するのはそれ以上の苦労があったと言われています。しかし、味の良さが次第に県民の評価を買い、栽培地や文旦を扱う農家が増えていったことで一大産地までに発展していきました。そのため高知県は土佐文旦の発祥の地としても知られているのです。その後に県内では水晶文旦も栽培されるようになりましたが、実は謎が多く、土佐文旦と別の種の交雑によって誕生したという説や偶然見つけたといった説もあるものの、その発祥や時代、誕生まで経緯などは不明となっています。本格的に水晶文旦が栽培されるようになったのは昭和後期、高知県に住む世界で初めてハウスみかんの栽培に成功した農家が、水晶文旦の性質がハウス栽培向きだと気づいたことによりハウスでの栽培をはじめ、生産を拡大させていったと言われています。
品種によって甘みの強さや食感は変わりますが、文旦の甘さは蜂蜜の成分と同じ果糖であるため、上品で優しい甘さを感じられます。また、ビタミンCやクエン酸、ミネラルなどの栄養素も豊富に含まれており、シミ・シワの予防や免疫力の向上、疲労回復といった効果が期待出来るだけでなく、血圧や中性脂肪を下げる・不眠の軽減などに効果的なギャバ(GABA)や発ガンを制御する力を持つオーラプテンなども含まれていることから近年注目がさらに集まっています。コツを掴めば簡単に皮を剥くことが出来るため、そのままだけでなくゼリーやジャム、皮のピールなど好みのぜひ高知県産の美味しい文旦の食べ方を見つけてみて下さい。専用の皮剥き器も販売されており、包丁よりも簡単で綺麗に皮を剥くことが出来るため、文旦をはじめとする大きめの柑橘類を食べる機会が多い方には皮剥き器を使うのもおすすめです。
芋けんぴ
“芋けんぴ”は細く切ったさつまいもを油で揚げ、グラニュー糖などの砂糖蜜を絡めた和菓子です。砂糖の甘さとさつまいもの風味、ポリポリとした食感を味わえるのが特徴で、古くからおやつとして食べられ、今や日本を代表する国民的なおやつとして人気を維持していきました。近年はさつまいもの品種が増えており、それぞれの食感や甘みといった特徴も異なっていることから、さつまいもを使ったスイーツが増えています。そのため、馴染み深い芋けんぴや干しいもなどもさまざまな品種で作られた商品が多数販売されており、子供から大人まで幅広い世代に愛されているどころかファンは増え続けている一方です。日本全国で食べられている芋けんぴですが、もともとは高知県で誕生したお菓子であり、名前についている「けんぴ」は高知県の郷土菓子である「ケンピ」から付けられています。ケンピ(堅干)とは小麦粉・砂糖・卵などを使った生地を焼き上げた干菓子で、歴史も古く、江戸時代から食べられていたと言われています。そのケンピにさつまいもを細切りにした形状や揚げた食感が似ていたことから芋けんぴと呼ばれるようになったそうです。さつまいもを油で揚げたシンプルなお菓子ですが、砂糖蜜でコーティングされているため油っこくなく、香ばしい風味と硬めの食感を楽しめるのも人気の秘訣となっており、以前は高知県の定番のお土産として扱われていましたが、自宅でも手軽に作れることやサツマイモを使っていることからヘルシーで健康やダイエットにも向いていたため、次第に日本各地でも食べられるようになったと言われています。
高知県では江戸時代からケンピという干菓子を食べていたことに加えて、薩摩から伝わったさつまいもを栽培するようになりました。土佐の風土や気候はさつまいもを栽培するのに適していたため、生産量が増えて庶民にも浸透し、貴重だった油や砂糖を使って作るさつまいも菓子はハレの日などの特別な日に食べるために作られるようになっていったそうです。県内で芋けんぴとして広まるようになったのは戦後間もない頃、当時青年だった高岡郡にある老舗芋菓子メーカーの創業者がかりんとうを作って自転車で販売するようになりましたが、食糧難で原料の小麦粉が高騰し、代わりにさつまいもを使うようになったのがきっかけとなります。甘くてポリポリとした食感と手軽さから瞬く間にお茶の間に広まり、ルーツであるケンピと共に高知県の名物へと発展していきました。その後も、丸い形をしたものやごまがかかっているもの、細さが違うもの、芋の種類や砂糖の種類が違うものなどが次々と誕生し、近年はチョコレートがかかっている芋けんぴも販売されるなど、年々芋けんぴは進化する一方です。さまざまな種類がある中でも特に人気が高いのが塩けんぴと呼ばれる種類で、砂糖蜜の甘さに塩の塩味と旨みが合わさった甘じょっぱい味わいは、ついつい手が進んでしまうほどの美味しさを持っています。また、バターを使っているものもバターの塩味とコクが深みを生み、塩けんぴとは一味違う美味しさを楽しめるため人気が高まっています。芋けんぴ発祥の地でもあることから、県内には芋けんぴや芋菓子を専門に扱うメーカーやブランドも多く、定番の味から柚子やレモン、キャラメル、チーズ、トリュフなど他県では見かけないようなフレーバーも多く扱っています。さつまいもの種類による風味の違いを味わいたい場合はプレーンを、いつもとは違った食感や風味を楽しみたい場合はフレーバー付きを選ぶと新しい発見に繋がるかもしれません。また、形やメーカーによっても食感が大きく変わってくるため、芋けんぴの食べ比べをするのもおすすめです。その際にはぜひ、ルーツとなった干菓子のケンピも一緒に食べ比べてみてもらいたいです。
アイスクリン
暑い日に食べたくなるアイスクリームですが、使われている乳成分の量によって種類が変わり、乳成分の量が多い順にアイスクリーム・アイスミルク・ラクトアイス・氷菓と大きく4つに分けられています。よくパッケージに記載されている表記が異なるのは乳成分の量に関係していたのです。さらに、口当たりや風味、濃厚さなども異なり、夏は氷菓、冬はアイスクリームが増えるなど、季節によって好む傾向も変わるため、販売される商品も変動することが多くなっています。実は奥が深いアイスクリームですが、高知県には“アイスクリン”という県を代表するスイーツがあり、この4種類にはどこにも当てはまらないような食感や風味を楽しめるのが大きな特徴です。他県民からするとあまり馴染みのないアイスクリンは、好きなフレーバーをコーンに乗せて食べるのが定番であるため、見た目はどう見てもアイスクリームですが、乳成分の割合が低く、ジャンルとしては氷菓の仲間になります。しかし、かき氷というよりもシャーベットに近くラクトアイス寄り、シャリシャリ・サクサクとした特有の食感とあっさりとした甘さや味わいはどの種類のアイスクリームには当てはまらず、アイスクリンでしか体感することが出来ないでしょう。また、氷菓の仲間であるためカロリーが低めであるのも特徴で、一般的なアイス100mlが約180kcalであるのに対してアイスクリンは100kcal前後になります。
アイスクリンの発祥は実は高知ではなく、横浜になります。明治初期に日本で初めて作られたアイスクリームを「あいすくりん」と呼んで販売し、欧米人を接待する際には欠かせない食べ物として浸透していきました。その後、戦争よって物資が不足したことで脱脂粉乳や卵を使うようになったこと、儲けが出ないことなどから一度アイスクリンの販売も激減してしまいましたが、自動車が普及するようになると移動式のアイスクリン店が急増し、日本全国に広まっていったと言われています。そのため、20年ほど前までは日本各地で購入することが出来るスイーツでしたが、物資が流通するようになると少しずつ乳成分の割合が高いアイスクリームが好まれるようになり、カップアイスなどの商品が増えたことでアイスクリンの需要が減ってしまいました。こうした経緯から、今でも昔ながらのアイスクリンが味わえる高知県は全国から見ても珍しく、名物として認知されているのです。アイスクリンの醍醐味といえば目印になるパラソルと移動式の販売所であり、公園や道の駅、国道沿い、観光地など県内のさまざまなところで購入することが出来ます。また、商店街や居酒屋、店舗によっては県外のアンテナショップなどでも販売されており、近年はカップタイプのものも販売しているため取り寄せることも可能です。県内にはアイスクリンを作る会社が多数残っており、フレーバーは定番のバナナをはじめ抹茶やチョコレート、イチゴ、柚子、あずき、メロンなど豊富な種類があるのもアイスクリームと間違われる理由かもしれません。幻の地鶏と呼ばれている土佐ジローの卵を使ったフレーバーなど高知県らしさを感じられる種類もあるため、食べたことがあるという人もパラソルを見かけた際には立ちよって、懐かしい思い出に浸ってみてはいかがでしょうか。反対に初めて食べる人はあっさりとした風味や特有の食感などアイスクリンの魅力をしっかり体感してみて下さい。