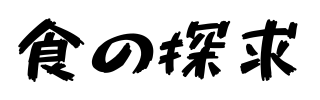味噌の種類の中では全体の約80%を占めているのが米みそです。
主原料の大豆に米麹と塩を加えて作られており、甘口・辛口、赤・白などを分けると6種類の味噌に分類することが出来ます。一般的なものの熟成期間は6カ月~1年前後、塩分濃度は5~13%のものが多いです。
味に癖がなく作り方や味の種類も豊富なため全国で生産・販売され、日本で一番食べる機会が多い味噌になります。
米みその作り方
①蒸した米に種麹をつけて米麹をつくる
②大豆を水に浸し蒸すor煮る → つぶして下処理をする
③下処理した大豆・米麹・塩・水を混ぜ合わせ桶に入れる → 発酵・熟成させて完成
味噌の製造工程はとてもシンプルです。
ですが、大豆を蒸すのか煮るのか、麹の量や熟成させる期間など製造過程のちょっとした違いで味や色の違いが出ます。味噌にたくさんの種類のあるのは、この少しの違いなのです。
米みその種類
味噌は種類が多いので細かい分類はありませんが、大きく分けると下記の3つから分類が出来ています。
①麹の違い ②味の違い ③色の違い
・米みそ ・甘みそ ・赤系みそ
・麦みそ ・甘口みそ ・淡色系みそ
・豆みそ ・辛口みそ ・白みそ
・調合みそ
特に米みそは生産されている種類が多いので、他の味噌に比べると分類が多く6種類に分けることが出来ます。
| 分類 | 味による分類 | 色による分類 | 麹歩合 | 塩分濃度 | 代表的な産地 |
| 米みそ | 甘みそ | 白 | 15~30(20) | 5~7(5.5) | 近畿、岡山、広島、山口、香川 |
| | | 赤 | 12~20(15) | 5~7(5.5) | 東京 |
| | 甘口みそ | 淡色 | 8~15(12) | 7~12(7) | 静岡、北陸 |
| | | 赤 | 10~15(14) | 11~13(12) | 徳島 |
| | 辛口みそ | 淡色 | 5~10(6) | 11~13(12) | 関東甲信越、北陸 |
| | | 赤 | 5~10(6) | 11~13(12.5) | 関東甲信越、東北、北海道 |
赤みそ・白みそ
米みその中には普段使っている“赤みそ”と“白みそ”も含まれますが、意外と何が違うのかよく分からない人も多いのではないでしょうか?色以外にどのような違いがあるのでしょう?
まず、製造方法が違います。
赤みそ
そのままの大豆を長時間浸してから蒸して作ります。これによりメイラード反応が起きやすくなり、赤褐色の色になるのです。
熟成期間は1年と長くコクがある
塩分濃度は10~20%と高いので味は濃くしょっぱい
メイラード反応とは・・・原料の大豆などに含まれるアミノ酸が糖に反応して褐色に変化すること。熟成期間が長いほど色が濃くなりますが、製品になってからも熟成が進むので時間がたつほど色はさらに濃くなるのが特徴です。
白みそ
大豆の薄皮を取り除き煮て作ります。
煮ることにより全体の水分が多くなり、メイラード反応が起きにくいように作ることで色が白っぽくなります。
熟成期間は約1か月と短く甘みが強いのが特徴。塩分濃度は5~6%になります。
これはよく目にする赤みそ・白みその違いです。しかし、上の表を見ると分かるように、味による分類の3種類には赤みそがすべて含まれています。その中でも甘みそと呼ばれる分類の中の赤みそは塩分濃度が5~7%と低く白みそとほとんど変わらなくなります。
また、赤みそは東北で愛用されている米から作られた赤みそが有名ですが、東海地方では豆から作られる味噌を赤みそと呼びます。
このように、赤みそ1つとっても種類が多いのが分かりますね。
次に6種類に分かれている味噌はどこの地域が好んで使っているのでしょうか。細かく見ていきましょう。
甘みそ
白みそ:近畿各府県、広島、岡山、山口、香川
京都|西京味噌:米麹の割合がとても高く甘みが強いです。懐石料理をはじめとした京料理に使われており、関西のお雑煮と言えば白みそを使う家庭が一般的です。
おすすめ料理・郷土料理:西京漬け、西京焼き、お雑煮
広島|府中味噌:こちらも米麹の割合が高いので甘みが強く、白やクリーム色をした味噌です。自然発酵で時間をかけて熟成させており、まろやかな味わいとなっています。塩分も控えめなため、より甘口に感じる味噌の1つです。
おすすめ料理・郷土料理:みそ汁、だんご汁、魚の漬け焼き
香川|讃岐味噌:熟成期間が1~2週間と特に短く、白く仕上げるため水を3~4回変えながら茹でて少しずつ色を抜いていきます。瀬戸内に面した海岸沿いの地域で作られており、濃厚な甘さが特徴です。
おすすめ料理・郷土料理:あん餅入りのお雑煮、打ち込みうどん
赤みそ:東京
東京|江戸甘みそ:地方色にとらわれない江戸独自で作り始めた味噌。白みそと違い蒸してから作るため赤色になりますが、大豆とほぼ同じ量の米麹を使うため塩分濃度が低く熟成期間も10日ほどと短く甘く仕上がります。さっぱりとした癖の少ない味が特徴です。
おすすめ料理・郷土料理:みそ田楽、どじょう汁、ホイル焼き
甘口みそ
淡色みそ:静岡、九州
静岡|相白みそ:静岡県、旧駿河の国中心に食べられてきた味噌です。白みそと田舎みその特徴を併せ持つことから相白(あいじろ)みそと呼ばれるようになりました。京都の白みそなどに比べるとそこまで甘くはないですが、熟成期間が5~20日と短く普通の味噌に比べると甘口。マイルドながらもさっぱりとしたご当地味噌です。
おすすめ料理・郷土料理:とろろ汁、吉田うどん、クリームソース煮
赤みそ:徳島、他
徳島|御膳みそ:阿波藩主・蜂須賀公の御膳に供されたことから呼ばれるようになった味噌。麹の割合が高くやや甘めの味噌ですが、しっかり熟成しているので風味が豊かでコクもあり、香りがいいのが特徴です。
おすすめ料理・郷土料理:味噌おじや、焼き味噌、豚汁
甘口味噌と甘味噌の違いについてより詳しい解説はこちら
辛口みそ
淡色みそ:甲信越、東北を中心に全国
長野|信州みそ:長野は生産量が全国の40%と日本一です。武田信玄が兵糧として味噌を作らせたことから生産が盛んになりました。さっぱりとしながらもうま味があり、少し酸味のある芳香が特徴でどんな素材とも相性抜群の味噌です。
おすすめ料理・郷土料理:焼きおにぎり、味噌煮、五平餅、鯉こく
赤みそ:北海道、東北、甲信越の寒い地域を中心に全国
北海道|北海道みそ:北海道独自の味噌づくりが発展し、佐渡や新潟と交流が多かったことから佐渡みそに近い赤い味噌。麹の割合が高いため塩分が控えめで辛口のなかではマイルドな味噌です。癖が少なく、さっぱりしているので食材の味を引き立ててくれます。
おすすめ料理・郷土料理:ラーメン、石狩鍋、鉄砲鍋、ちゃんちゃん焼き
青森|津軽みそ:麹の割合が低く塩分が高いですが熟成期間が長いため、独特のうま味がある味噌です。
おすすめ料理・郷土料理:けの汁、じゃっぱ汁、貝焼きみそ、せんべい汁
秋田|秋田みそ:辛口の赤みそですが良質な米と大豆を使っているため、他の東北の赤みそに比べると麹の割合が高めで甘みやうま味が感じられます。
おすすめ料理・郷土料理:石焼き鍋、いものこ汁、焼き味噌きりたんぽ
新潟|越後みそ・佐渡みそ:越後みそは精米した丸米をそのまま使用するので米粒が味噌の中に浮いているように見えることから“浮麹みそ”とも呼ばれています。佐渡みそは大豆が多く使われているためコクがあり大豆のうま味を感じる味噌となっています。
おすすめ料理・郷土料理:しょっから煮、のっぺい汁、味噌炒め
他にも宮城の仙台みそ、福島の会津みそ、石川の加賀みそなど辛口の赤みそは種類が味噌の中でも特に多く、同じ県内だけで探しても特徴のある赤みそが多種見つかります。
東北地方は歴史が長くまた厳しい気候の中で長期間かけて作られた味噌が多いため辛めの印象の味噌が多く感じられました。
このように米みそと言っても本当に種類が多く、分類されていたとしても数えきれない種類の味噌があります。
また、地域によって作られてきた過程や歴史、環境も大きく影響するので特徴や見た目、味の違いも一緒に大きく変わってくるのが米みその良さでもあり面白さでもあります。