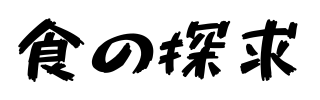みなさんは“ぬか炊き(ぬかだき)”という言葉をご存じですか?
あまり聞いたことがない人でもぬかを使っているのはなんとなく分かるかと思います。ぬか炊きはテレビ番組のケンミンショーでも取り上げられる県民食です。しかし名前だけでは調理方法なのか食べ物なのか、食べ物だとしてもどのようなものを使っているのかピン来ない人もいるのではないでしょうか。今回はそんな“ぬか炊き”について調べてみました。
ぬか炊きとは
はじめにお伝えするとぬか炊きとは、福岡県北九州市小倉に古くから伝わる郷土料理です。
「ぬか味噌炊き」や「じんだ煮」とも呼ばれていて、サバやイワシなどの青魚を醤油などの調味料と煮る時に、ぬか床のぬか味噌を一握り一緒に入れて炊いています。ぬか味噌を一緒に炊くことにより青魚の臭みを消すだけでなく、ぬか味噌のうま味が青魚に染み込み美味しさにも繋がっているようです。
もともとは青魚を調理するために使われていましたが、現在ではサバ、イワシだけでなく他にもさんまやちりめん、鶏肉、筍、しいたけなどさまざまな食材を使ったぬか炊きがあります。
小倉を中心におかずやお酒のつまみとして年間通して食べられていますが、正月や葬式などの冠婚葬祭の時にも食べられている北九州では馴染み深い食文化の1つとなっています。
ぬか炊きの作り方
1番スタンダードなぬか炊きの作り方としては下記のような手順になります。
- 1.サバやイワシなどの青魚をさばく またはさばいた青魚を用意する
- 2.醤油・砂糖・みりん・酒などの調味料と一緒に煮る
- 3.魚にある程度火が通ったらぬか味噌を加え、弱火よりさらに弱めの火でトロっとするまで煮る
お店やレシピによってはみりんや酒、生姜を入れたり入れなかったり、使う醤油やだしの有無などに違いがあります。本格的なぬか炊きまでとはいかなくても、簡単に作れてしまうため味の違いや青魚以外の食材をを試してみるのも新しい発見に繋がるかもしれませんね。
ぬか炊きの歴史
ぬか炊きの歴史は古く、江戸時代まで遡ります。江戸時代初期に伝わったぬか漬けを当時の小倉藩主が好んで食べていたことがきっかけで城下町にも広まり、保存食として食べられていました。
現在のぬか炊きの原形となる醤油や砂糖、酒などの調味料を加え始めたのは江戸時代中期頃のようです。
この頃から北九州ではぬか床を使ったぬか漬けやぬか炊きが愛されています。そのため、大切に育てられたぬか床を先祖代々受け継いでいっているのです。嫁入り道具としても次の世代へと受け継いできたぬか床は50年近いものも多く、長いものだと100年以上の歴史のあるぬか床を使っている家庭もあるのだとか。
そんな歴史のある小倉のぬか床は、昆布や唐辛子と一緒に山椒を入れているのが特徴です。ピリッとした味わいのあるぬか床には長い年月をかけて浸けてきた野菜のうま味がたくさん詰まっており、そのうま味がぬか炊きに使うことで青魚にも影響するのです。
体にもよい?ぬか炊きの栄養分
青魚を炊くときに入れるぬか味噌の素となっているぬか床は長い年月をかけて作られています。ぬか床は毎日かき混ぜることによってたくさんの乳酸菌や酵母菌が発酵・熟成を繰り返しうま味成分へと成長します。
さらに、ぬか床にはビタミンやミネラルも豊富に含んでいて、長時間かけて煮た青魚は骨まで食べられるものが多いため、カルシウムやDHAなども一緒に美味しく体に取り入れることが出来る健康にも美容にもよい食品になっています。
ぬか炊きはどこで食べられるのか
そんな体によいことが多いぬか炊きは一体どこで食べられるのでしょうか。
小倉地域では、居酒屋や食堂などの飲食店で食べられることが多いようです。他県でとなると簡単には食べられることは少なくなりますが、北九州や各都道府県の料理を提供している居酒屋などの飲食店で食べられるお店があるそうです。
近場にお店がないという人は、通販でも取り寄せ可能な商品があります。一部を紹介しますね。
- Amazon
https://www.amazon.co.jp/%E3%81%AC%E3%81%8B%E7%82%8A%E3%81%8D/s?k=%E3%81%AC%E3%81%8B%E7%82%8A%E3%81%8D - がんこ母さんのぬかだき
https://www.aziyoshi.co.jp/ - ぬかみそだきのふじた
https://nukamisofujita.com/ - かねすえ本舗
https://www.kanesuehonpo.co.jp/ - 福岡県よかもんショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/bussan-f/ - 北九州酒場 西新宿店
https://kitakyushusakaba.owst.jp/ - 手料理 おおよそ(銀座)
https://retty.me/area/PRE13/ARE2/SUB201/100001418206/
など、ぬか炊きを作っているメーカーのサイトや九州・福岡のご当地品を扱っているサイトから直接購入することが出来ます。ふるなびなどのふるさと納税のサイトでも取り扱いがあったり、各地にあるアンテナショップや物産展でも買えることがありますので気になった人はチェックしてみて下さい。
いかがでしたか?ぬか炊きは美味しいだけでなく、健康や美容にもいいことがいっぱいであることが分かりましたね。ご飯のお供としてそのまま食べるのもよいですが、野菜と炒めたりうどんなどの具材として乗せるなどアレンジも豊富なぬか炊き。まだ味わったことのない人はぜひ一度味わってみて下さい。