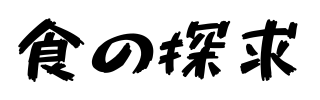味噌には原材料の違いや歩合率などによりいくつかに種類が分かれます。その中でも甘口味噌、甘味噌と呼ばれる味噌があり、実は味噌は異なる味噌であるとご存じでしたか?この2つにはどのような違いがあるのか調べてみたのでご紹介していきます。
甘口味噌と甘味噌の違い
まず、甘口味噌と甘味噌とは米味噌と呼ばれる味噌の中で、使われている麹の歩合と塩分濃度の違いから分けられている種類となります。米味噌の中で1番麹の歩合が高く塩分濃度が低い甘みが強い味噌が「甘味噌」、甘味噌より麹の歩合も塩分濃度も低くバランスが良い味噌が「甘口味噌」になります。
甘味噌と甘口味噌の比較
塩分濃度が高い:甘口味噌
麹の歩合が高い:甘味噌
つまり、甘味噌と甘口味噌を比べると、塩気が強い味噌が甘口味噌で、塩気が少なくその名通り甘目な味噌が甘味噌となります。麹は炭水化物であり、糖に変わるため、麹が多いと甘く感じるという具合です。実際下の表をみていただけると辛口は最も麹の量が少なく、甘味噌になると麹の量が増えていることがわかります。正確には辛口、甘口、甘と3分類ですが、辛口味噌と甘味噌の中間点をその名の通り中辛と表現することもあるようです。
流通している味噌の多くが甘口味噌と言われており、普段口にする味噌は甘口に分類されることが多いと言えます。甘口味噌は塩分濃度が高くなりますが、大豆の旨味も効いてくることからお酒が好きな方がおつまみを作る際に使用したり、お酒のアテにきゅうりに味噌をつけてというシーンでは甘口味噌や辛口味噌が合うのではないでしょうか?また、甘味噌は麹が多く甘く感じられることから小さなお子さんが味噌汁等で食べる際にはウケが良いと言われています。
はじめにもお伝えしたように、味噌は原材料や歩合、塩の量によっていくつかの種類に分かれます。原材料は“大豆・麹・塩”となりますが、使う麹が米麹なら「米味噌」、麦麹なら「麦味噌」、大豆に直接麹を付けて作っている場合は「豆味噌」になります。
より詳しい米味噌の解説はこちら
さらに米味噌は甘口味噌・甘味噌に加え辛口味噌の3つに分かれ、生産地によっても味噌の香りや味、色などの特徴が大きく違ってきます。米味噌の中では1番麹の歩合が低く塩分濃度が高いものを辛口味噌と呼んでおり、主に長野や東北などの寒い地方で作られている味噌となります。大きく分けるとまず辛口・甘口味噌と甘味噌の2つに分けられ、歩合や塩分の違いからさらに辛口と甘口に分かれているイメージです。そこに熟成期間や製法の違い、大豆に含まれるアミノ酸が糖と結合することにより起こるメイラード反応により色が分けられ、辛口・甘口は淡色か赤の2種類、甘味噌は白と赤の2種類に分かれています。
| 麹の歩合 | 塩分濃度 | 産地 | ||
| 辛口味噌 | 淡色 | 5~10 | 11~13 | 甲信越・北陸中心に全国 |
| 赤 | 甲信越・東北・北海道中心に全国 | |||
| 甘口味噌 | 淡色 | 8~15 | 7~12 | 静岡・九州 |
| 赤 | 10~15 | 11~13 | 徳島 他 | |
| 甘味噌 | 白 | 15~30 | 5~7 | 近畿各府県・岡山・広島・山口・香川 |
| 赤 | 12~20 | 東京 | ||
参考:ひかりみそ https://www.hikarimiso.co.jp/enjoy-miso/encyclopedia/type.html
甘口味噌と甘味噌を料理で使い分ける
甘口味噌と甘味噌は先ほど解説した通りの違いとなりますが、料理ではどのように使い分けると良いでしょうか?あくまで好みの範囲となりますが、編集部でのおすすめを紹介したいと思います。
甘口味噌
甘口味噌は麹の甘さと塩気のバランスがよく辛口味噌と甘味噌の中間であり、万能選手と言えます。そのため辛口味噌を使用する料理、甘味噌を使用する料理で分けることはありますが、どっちを買うのも面倒という時は甘口味噌を常備しておけば良いのではないでしょうか?そのため料理の使い分けの解説としましたが、甘口味噌だから向いているという料理はあまりなく、辛口味噌、甘味噌どちらの料理にも使用できる味噌です。
甘味噌
逆に甘味噌は甘味の強い特徴がある味噌です。そのため、その甘さを生かした料理に向いており、編集部では淡白な白身魚を使用した西京焼き、大根やにんじんなどの根菜を使用した味噌汁、里芋と野菜の煮物などに使用する良いのではないでしょうか?逆に、豚肉など素材の甘みが強い食材には辛口味噌のほうが向いているように感じました。素材が甘いときはあえて調味料は塩気が強いタイプを使用するとその差により甘さを引き立てる効果があるそうです。そのため、淡白で甘味の少ない食材には甘味噌が合うのではないでしょうか?
地域ごとの甘口味噌と甘味噌の紹介
味噌のような伝統的な調味料は、JASで定める区分とは信州味噌や越中味噌のように地域で独自の発展をしている、味噌が存在します。最後に甘口味噌、甘味噌に該当する味噌で、地域独自の文化を反映した味噌を紹介したいと思います。
甘口味噌 淡色/赤
甘口味噌は流通している商品数が多く、メーカーや味噌蔵、作られている地域によっても味の違いが1番多いです。甘く感じるものから甘辛いものまで種類もさまざまで、麹の歩合や塩分濃度のバランスが良いため全体的にマイルドでとても食べやすい味噌になります。さらに熟成期間が4~8か月のものが淡色という扱いになり、現在は甘口の淡色が一般的には主流となっています。代表的な甘口味噌の淡色には富山の越中味噌や静岡の相白味噌があります。
熟成期間が淡色よりも長く1年以上熟成させているものが赤になり、色の濃い赤褐色の見た目と強いうま味が特徴です。甘口の淡色に比べると麹の歩合も塩分濃度も高くなるため香りがよくコクも感じられます。しかし、生産されている産地が少なく全体的には生産量は少なめです。代表的な甘口味噌の赤には徳島の御膳味噌があり蜂須賀公の御膳に供されたことから呼ばれるようになったという歴史もあります。
甘味噌 白/赤
甘口味噌に対してさらに麹の歩合が高く塩分濃度が低い味噌が甘味噌となります。甘味噌は色が白と赤に分かれますが赤は種類が少ないため白の方が主流となり、一般的に販売している白味噌は甘味噌に該当します。産地も使う頻度も関西圏から中国・四国地方が特に多く、京都の西京白味噌や広島の府中味噌、香川の讃岐味噌が代表的です。どれも白くクリーミー、甘みが強いのが特徴で熟成期間は1か月ほどと非常に短いため、大豆に近い白っぽい色をしています。基本甘みが強い味噌となりますが、なかには塩分濃度が高めに作られている味噌も存在します。中国・四国地方は甘味噌に次いで甘味を感じられる麦味噌を主流に使うことが多いことから、甘めの味噌を好む傾向が強いです。
甘味噌の赤と言えば江戸甘味噌が有名で代表的です。江戸独自に作られた江戸甘味噌は熟成期間は10日とさらに短く米麹の割合が高いため、濃厚な甘味と独特な香りがあります。関東は基本的に辛口味噌を使いますが、甘辛い味付けが特徴の江戸の料理には欠かせない味噌でどじょう鍋などにも使われています。
甘口味噌と甘味噌は文字だけで見ると違いが分かりづらいですが、甘口味噌は甘めの一般的な茶色い味噌、甘味噌は白味噌ということになります。もちろん色の違いや塩分の違いによって細かく分けることは出来ますが、大きな目安として覚えておくとどのような特徴なのかが分かりやすく、購入する際や料理で使う際に迷わなくて済みます。さらに把握しておくことで産地別の味噌の特徴や違いが分かりやすくなるのでぜひ参考にしてみてくださいね。