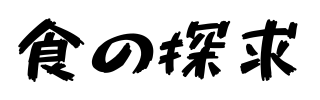赤味噌、田舎味噌、麦味噌、たくさんの種類があり、なんとなく普段から使い分けている味噌。醤油などは古くからJAS法によって明確に区分がされていましたが、実は味噌がJAS法により明確に区分されたのは2022年とつい最近のできごとです。今回はJAS法に基づく味噌の区分と、特徴を解説していきます。
味噌が区分されるようになった背景
味噌は赤味噌、麦味噌、白味噌のように地域の食材や文化、風土を反映し地域色の強い調味料の1つです。従来は地域色を大切にしながら伝統的な手法や新しい製造方法が組み込まれたりし伝統の維持や進化が行われてきました。
しかし、昨今の日本食ブームにより海外に味噌が輸出される量が増えると、味噌を模した海外の大豆発酵商品が味噌という名で安価に販売されており、海外市場で競争にさらされるようになりました。また、国際規格であるCodex規格では、日本の味噌を含むアジア地域の大豆発酵食は「発酵大豆ペースト」としてカテゴライズされており、日本の伝統的な味噌の意味合いや文化、特徴などが海外市場において十分に伝わらないという課題がありました。
そこで、JAS法により味噌を定義し、製造方法と原材料による区分を設けることで、海外の大豆発酵商品と差別化を図るため、JAS法による区分がされました。これにより海外での味噌の競争力を高め、他アジア諸国の大豆発酵食品と差別化を図り、より味噌の輸出量を拡大することを狙っています。
“味噌とは
JASによると味噌とは下記のように定義されています。
次に掲げるものであって,半固体状のもの
a) 大豆若しくは大豆及び米,麦等の穀類を蒸煮したものに,米,麦等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを
加えたもの又は大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの若しくはこれに米,麦等の穀類を蒸煮したものを加えた
ものに食塩を混合し,これを発酵させ,及び熟成させたもの
b) a)に砂糖類,風味原料等を加えたもの”
ポイントとなるのは、「こうじ菌」が使用されていることで、別注の用語においてこうじ菌はAspergillus oryzae であることという定義がされています。Aspergillus oryzae はユートチウム科コウジカビ属に属するニホンコウジカビのことで、不完全菌の1つです。このこうじ菌を使用していることが味噌の定義に重要であり、他の麹、例えば乳酸期の四連球菌、ケカビ目などは含まれません。また逆に言えば、こうじ菌を使用して作られる味噌は国内で生産されたもの限っていはいないため、海外で生産されてもAspergillus oryzae を使用し生産された味噌は味噌と呼ぶこともできます。
味噌の種類
味噌は、原材料によって区分され米みそ、麦みそ、豆みそ、調合みその4つに区分されます。JASではみそとひらがなの表記を使用しています。
米みそは大豆、ばらこうじ(米を原料としているもの)、食塩で作られ、麦みそは大豆、ばらこうじ(麦を原料としているもの)、食塩で作られます。米みそ、麦みそは使用するばらこうじの原料によって分かれます。豆みそは豆こうじと食塩で作られ、調合みそは米みそ、麦みそ、豆みそ以外のみそとされ、例えば、米みそ、麦みそを製造後に混合したものを合わせみそと呼びます。合わせみそをスーパー等で見かけた際には、Aspergillus oryzae を使用した米、麦、豆いずれかの味噌で、それらをブレンドした味噌だ、ということになります。
一般的に米みそ、麦みそ、豆みその順で醸造期間が長くなります。また、よく聞く白味噌、赤味噌などの区分はJAS法によって定められてはいないものの、最終的に製造され完成された味噌の色によって決められ(定義はないためそう呼ばれる)、醸造期間が長くなればなるほど赤みを帯びるとされています。
米みそ
米みそは大豆、こめこうじ、食塩から作られる味噌です。米みそは年間およそ40万トン製造されており、国内で製造される味噌の85%を米みそが占めます。JAS法では米みその他、麦みそ、豆みそ、調合みその4種類の区分しかありませんが、一般的に色と味わいで更に細分化されます。以下はJAS法ではなく一般的な区分です。
| 分類 | 味による分類 | 色による分類 | 代表的な産地 | 代表的な味噌 |
| 米みそ | 甘味噌 | 白 | 近畿、岡山、広島、山口、香川 | 関西白味噌、讃岐白味噌、府中白味噌 |
| 赤 | 東京 | 江戸甘味噌 | ||
| 甘口味噌 | 淡色 | 静岡、北陸 | 越中味噌 | |
| 赤 | 徳島 | 御膳味噌 | ||
| 辛口味噌 | 淡色 | 関東甲信越、北陸 | 信州味噌 | |
| 赤 | 関東甲信越、東北、北海道 | 北海道味噌、津軽味噌、秋田味噌、仙台味噌、 会津味噌、佐渡味噌、越後味噌、加賀味噌 |
甘味噌は塩分濃度が6〜7%、甘口味噌は10%前後、辛口味噌は12%前後と塩分濃度によって分かれていきます。甘味噌は甘いものから塩辛いものまで様々で、地域や作り方によって様々あることが特徴です。甘口は九州、四国、関西地方で好まれ、甘口味噌は中部、北陸、辛口味噌は関東、東北地方で好まれる傾向があります。地域で区分するとそのような特徴がありますが、東京は辛口味噌より甘味噌が好まれるなど、都道府県単位でも好まれる味噌の差はあり、この地域だから甘味噌、というよりはこの県、市区町村はこの味噌というように地域にどのような味噌蔵(味噌メーカー)が根ざしているかで違いがあるようです。余談ですが、醤油も似ており西に行けば行くほど甘く、東に行けば行くほど辛い(塩分が増える)傾向があります。
色による区分は、主に熟成期間によって異なり、熟成期間が長くなればなるほど赤みが強くなります。白色の味噌は甘味噌ですが、赤味噌と一言で言っても、甘味噌、甘口味噌、辛口味噌それぞれに赤色の味噌が存在しており、赤味噌=〇〇味噌!とも言えません。また後ほど説明しますが、愛知県で好まれる赤色をした豆味噌を赤味噌と呼ぶこともあります。このうように米みそは様々な味と色が存在しています。
より詳しい米みその解説はこちら
麦みそ
麦みそは、大豆、むぎこうじ、食塩から作られる味噌で、JAS法による4つの区分では最も少ない生産量の味噌とされています。主に九州、四国地方で好まれる味噌で、大麦かはだか麦を使用します。今でこそ九州地方もお米の生産が盛んですが、温暖な気候で米が作りにくく麦を多く生産していたという歴史的な背景から麦を使用した味噌作りが盛んであったからとされています。
麦みそも塩分濃度によって区分され甘口味噌と辛口味噌の2種類があります。辛口味噌は一部関東地方でも好まれる傾向がありますが、やはり麦味噌は九州、四国が中心と言えます。
より詳しい麦みその解説はこちら
豆味噌
豆みそは豆こうじと食塩で作られます。赤色をしており、甘みが少ないことが特徴です。いわゆる名古屋めしと言われる、味噌煮込みうどんなど味噌煮込みにはこの豆味噌が使われています。名古屋の赤味噌と言えば、つまり八丁味噌と広く認知されていますが、八丁味噌は当時2社で作られる豆味噌を指すものとされていました。この2社のブランドとしての名前なのか、愛知県で作られる豆味噌全般を指す名前なのか?という議論は裁判にまでいたり、2023年に愛知県で作られる豆味噌全般を指す言葉として一応の判決が出ています。
しかし、今後また八丁味噌という名前を使用することに対する議論はこれからも続きそうです。
より詳しい豆味噌の解説はこちら
調合みそ
調合味噌はJAS法では米みそ、麦みそ、豆みそ以外の味噌とされています。例えば、米みそ、麦みそを混ぜた味噌を合わせ味噌と呼んだり、ハトムギこうじを使用した味噌をハトムギ味噌と呼んだりします。
流通量は米みそに次ぐ第2位の流通量で、地域によって調合やこうじのもととなる原料が微妙に変わったりします。
以上味噌の区分と特徴でした。味噌は醤油のように地域によって様々な違いがあり、その地域に料理や風土に合わせて変化、進化をしてきました。旅行などその地域に訪れた際には、その地域で好まれる味噌を探して味わってみるのも良いかもしれません。
より詳しい調合みその解説はこちら